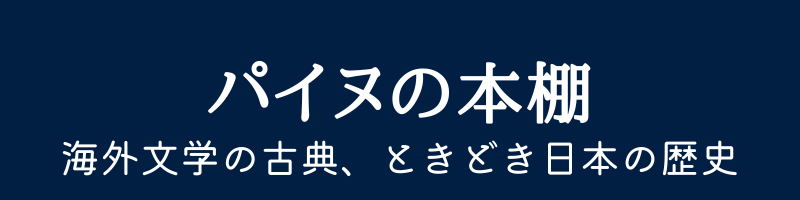この記事では、当ブログの
YouTubeチャンネルにおいて公開した
動画の内容をもとに
おすすめの本をご紹介しています。
動画をご覧になりたい方はこちらへ↓
https://www.youtube.com/@painubooks24
【1】ナイン・ストーリーズ
まず1冊目は、J・D・サリンジャーの
『ナイン・ストーリーズ』です。
新海誠監督の『天気の子』に
カップ麺のフタのフタ役として登場した
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』ですが、
その作者として知られる
J・D・サリンジャーです。
第二次世界大戦後の
アメリカ文学を語るうえでは
サリンジャーは避けては通れない存在で、
とりわけ、当時のアメリカ社会に与えた
影響の大きさを考えれば、
サリンジャーを読まずして、
戦後のアメリカを知ることはできない
といっても決して過言ではないと思います。
ただ、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は
ストーリーが結構長いので、
サリンジャーのスタイルに
慣れていない人にとっては
少し退屈に感じるかもしれません。
物語の内容自体も、人によって、
好き嫌いがはっきりと分かれる話
ではあるので、
ビギナーの人には
正直あまりおすすめしません。
反対に、私がおすすめしたいのが、
サリンジャーの『ナイン・ストーリーズ』
という作品です。
この作品はタイトル通り、
9つの短編小説を収録した
短編集になるんですけど、
サリンジャーらしさが
ギュッと凝縮された物語を
手軽に楽しむことができるので、
ビギナーの人にとっても
非常に手に取りやすいものとなっています。
この短編集のなかで
もっともよく知られているのは、
9つの物語のうち、トップバッターを務める
『バナナフィッシュにうってつけの日』
という作品です。
ちなみに、ここに出ている
河出文庫の柴田元幸訳では、
『バナナフィッシュ日和』
というタイトルになっています。
ストーリーは一見すると
非常にあっさりしていて
あっけない結末を迎えるんですが、
だからこそ、随所にちりばめられた
いくつもの謎が際立って、
あれはいったい
どういう意味だったんだろう?という
あとを引くような読後感を味わうことが
できると思います。
サリンジャーの小説というのは、
人によっては、
なにを言いたいのかよくわからないものに
映るかもしれませんが、
こういう「わけのわからなさ」というのも
ある意味では文学の醍醐味であって、
的確な言葉を介したものよりも、
場面や雰囲気といったものから
伝わってくるものを楽しむ、
そういうタイプの小説を知る
という意味においては、
サリンジャーの『ナイン・ストーリーズ』は
まさに、うってつけの作品だと思います。
【2】ハツカネズミと人間
つづいて2冊目は、
ジョン・スタインベックの
『ハツカネズミと人間』です。
まるで映画を観ているような気分で、
物語を楽しむことができる小説。
これが、スタインベックという作家の
一番のセールスポイントだと思います。
言葉を尽くしてメッセージを届けようとする
というよりはむしろ、
登場人物の表情や、周囲の情景を描写して、
それぞれの場面を映像として見せること
によって、
読者の想像力を刺激する、というのが、
スタインベックの手法でもあるんですね。
本作『ハツカネズミと人間』ではまさに、
映画のような演出の効果が
存分に発揮されていて、
シリアスな内容ながら、
テンポよく展開していく
ストーリーのおかげで、
テーマの濃密さが損なわれることなく、
気軽に物語を楽しむことが
できると思います。
『ハツカネズミと人間』の一番の見所は、
なんといってもやはり
あの衝撃のラストシーンで、
主人公の苦渋の選択には
心がかき乱されるような思いがするのと、
そこへもって、解放感と虚しさを
ないまぜにしたような
なんともいえない読後感が
押し寄せてきます。
それからもう一つ、
この作品の特徴として押さえておきたいのが
人々の「抑圧された願望」という点です。
この物語に出てくる主要人物たちは
なにかしらの「はかない夢」を
胸に秘めているんですけど、彼らは、
強烈なフラストレーションを抱えながらも
それぞれの「夢」を心の支えにして、
苦労の多い日々の生活を
なんとか耐え忍んでいるんですね。
主人公のジョージとレニーの場合には、
2人が自給自足して
普通に暮らしていけるだけの
ささやかな土地を手に入れて、
「土地のくれるいちばんいいものを
食って、暮らす」という夢があって、
一時は、ひょっとしたら
実現できるかもしれないという
見込みまであったものの、
運命のいたずらともいうべき理不尽によって
手のひらから砂がこぼれおちていくように
夢はあえなく潰えてしまいます。
農場で暮らす人々を取り巻く
息の詰まるような閉鎖的な環境と、
そこから逃げ出したいと願いつつも、
どこにも行く当てのない彼らの鬱憤が
手に取るように感じられて、
思わずぶるっと震えてしまいそうに
なりますが、
このような状況というのは
ただのフィクションでもなんでもなくて、
それこそ、シャーウッド・アンダスンの
『ワインズバーグ、オハイオ』の時代から
現在のいわゆる
「分断の時代」にいたるまで、
多くの人を苦しめてきた
見えざる手枷足枷でもあると
思うんですよね。
この問題を知っているのと知らないのとでは
社会に対する見方というのも
大きく変わってくることでしょうし、
アメリカ文学でもよく取り上げられる
スモールタウンの課題を知る
という意味においても、
非常に重要な作品だと思います。
【3】オー・ヘンリー傑作選
つづいて3冊目は、
『オー・ヘンリー傑作選』です。
オー・ヘンリーは
アメリカ文学のなかでも指折りの
短編小説の名手として知られる作家です。
その代表作である『賢者の贈り物』や
『最後の一葉』といった作品は、
子ども向けの絵本やアニメとして
アレンジされていることもあって、
ご存じの方も多いと思います。
オー・ヘンリーの魅力といえば、やはり、
ユーモアとウィットとペーソスの
見事なブレンド力で、
その手にかかれば
どんなにシリアスな状況も、
瞬く間にコミカルな情景へと
生まれ変わります。
短いストーリーのなかに
おもしろさと、うまさと、もの悲しさを
すべて組み込もうとすると、
普通であれば、話がこんがらがってしまう
ところなんですが、
オー・ヘンリーの場合、そうはならずに、
絶妙なバランスをキープしているところが
すごいんですよね。
大都会の片隅で
安い給料をやりくりしながら、
つつましく生活している
健気な若者たちがいる一方で、
退屈しのぎに
ちょっとした冒険に打って出る
お金持ちがいて、
恋を実らせる者がいたかと思えば、
現を抜かして痛い目を見る者がいて、
さらには、一人は犯罪者として、
もう一人は警察官として、
数十年ぶりの再会を果たした
かつての親友たちがいて。
こんな感じで、実にさまざまな人間模様を
垣間見ることができるというのも、
オー・ヘンリーならではの
おもしろさだと思います。
ちなみに、私のお気に入りは
『改心』という作品で、
ジミー・ヴァレンタインという
無敵の金庫破りが出てくる話なんですけど、
ジミーが犯罪から足を洗って、
新しい生活にすっかりなじんできたところへ
のっぴきならない騒動が
巻き起こってしまうんですね。
私はこの話のオチがとても好きなんですけど
オー・ヘンリーの作品には、いわゆる
善と悪の境界線を綱渡りしている人たち
というのがよく出てきて、
『改心』の主人公も
その一人だと思うのですが、
こういう人たちを
悪の領域へ突き離すのではなくて、
それとなく、善の領域へ
引き込んでいこうとするところに、
作者の情け深さが感じられて、
短いストーリーながらも
いいものを読んだなという気持ちに
させられます。
【4】ポー傑作選1
つづいて4冊目は、『ポー傑作選』です。
エドガー・アラン・ポーは、
アメリカ文学の歴史のなかでも
比較的初期の方に活躍した作家で、
フォークナーやヘミングウェイが
「アメリカ文学の父」として称賛する
マーク・トウェインよりも、
あるいは、『緋文字』のホーソーンや
『白鯨』のメルヴィルよりも前に、
数多くの作品を発表して、
アメリカの文壇を盛り上げた人物でも
あります。
つまり、マーク・トウェインが
「アメリカ文学の父」であるならば、
エドガー・アラン・ポーは
「アメリカ文学の祖父」にあたる
というわけですね。
この二人の文豪の作品を比較してみると、
アメリカ文化の変遷と、
その成熟ぶりが垣間見えて
非常に興味深いのですが、
マーク・トウェインの『トム・ソーヤー』や
『ハックルベリー・フィン』が
アメリカのほぼど真ん中を流れる
ミシシッピ川流域の田舎町を
舞台にしているのに対して、
エドガー・アラン・ポーの作品は、
どちらかといえば、
イギリスやフランスといった
ヨーロッパの文学、
アメリカの新世界に対して、
ヨーロッパは旧世界
と呼ばれたりもしますが、
この旧世界たるヨーロッパの文学に
強く影響を受けていることがわかります。
角川文庫から出ているこの本のタイトルにも
「ゴシック・ホラー編」と
銘打ってあるように、
エドガー・アラン・ポーの作品には、
ダークで、奇怪で、悪趣味なものが
うごめいていて、
ホラーはホラーでも、
魔術的な気味悪さというものに
焦点が当てられているような気がします。
ディズニーランドのアトラクションに
たとえると、
「ホーンテッドマンション」が醸し出す
あの陰湿な雰囲気を思い出してもらえれば、
なんとなくイメージを
つかんでもらえるのではないでしょうか。
ちなみに、私の個人的なお気に入りは、
『ウィリアム・ウィルソン』と
『メエルシュトレエムに呑まれて』
という作品で、
ポーの作品のなかでも、どちらかといえば、
「奇怪さ」というものが
色濃く出ている話になります。
ポーの作品は現在、各出版社から
さまざまな翻訳で発売されているので、
気軽に手に取りやすいものと
なっているのですが、
私が今回読んだ角川文庫のものには、
作品ごとの丁寧な解説と
作者の数奇な人生を追った簡潔な伝記が
巻末に収録されていて、
エドガー・アラン・ポーという
作家を知るための入門書としても、
一見の価値ありの内容となっています。
【5】グレート・ギャツビー
これで最後になります。
5冊目は、スコット・フィッツジェラルドの
『グレート・ギャツビー』です。
『グレート・ギャツビー』は
20世紀以降のアメリカ文学の歴史に
一つの支流を発生させたともいえる
記念すべき作品で、
この流れが、サリンジャーや
ジョン・アーヴィングといった作家に
つながっていくのだと考えると、
その存在の大きさというものを
改めて認識させられます。
日本の文学界では、この流れが、
小説家・村上春樹へつながっているそうで、
実際に、村上春樹の翻訳を通じて、
この作品を知ったという人も
少なくないかもしれません。
第一次世界大戦の
いわゆる「特需」によってもたらされた
アメリカの好景気の時代は
「狂乱/狂騒の時代」と呼ばれたり、
あるいは、スコット・フィッツジェラルドの
作品にちなんで、
「ジャズエイジ」と呼ばれたりも
するそうなんですが、
彼自身がまさに「時代の寵児」として、
当時のアメリカの文壇に
「当世風を送り込んだ」
とでもいいましょうか、
なんだか、そんな感じがするんですよね。
『グレート・ギャツビー』は
冒頭から結末までの流れを
一気に駆け抜けるようにして
ストーリーが展開していくんですが、
登場人物たちの関係性をはじめとする
物語の細かい設定にまで目を向けると、
なかなか複雑な要素が絡まり合っている
ということがよくわかります。
戦争によって引き裂かれてしまった
昔の恋人を取り戻すために
わずか数年のうちに、一文無しの境遇から
大富豪の地位へと登りつめた
ギャツビーでしたが、
愛しのデイジーとの間に
ぽっかり空いてしまった「時間の差」を
埋め合わせすることは、ついにかなわず、
事態は思わぬ方向へ転がっていきます。
ニューヨークのロングアイランドにおける
2人のきらびやかな暮らしの背後には
「戦争」「格差」「犯罪」という
陰湿な黒い影がうごめいていて、
このような光と影のコントラストが
当時のアメリカ社会を
立体的に再現しているようで
非常に興味深いのですが、
このほかにも、この小説には、
象徴的なモチーフといいますか、
暗号めいたメッセージのようなものが
いくつか出てきて、
読者の想像を大いにかき立てます。
「T・J・エクルバーグ博士の看板」とか、
「灰の谷」とか、「緑の灯火」とか、
あと、「階段の落書き」とか、
こういったものが意味深長なシンボルとして
物語の随所にちりばめられているんですけど
これはいったい
なにを表現しているんだろう?と
自分なりに考えてみると、
物語に秘められた「もう一つの意味」が
ぼんやりと浮かんできて
おもしろいんですよね。