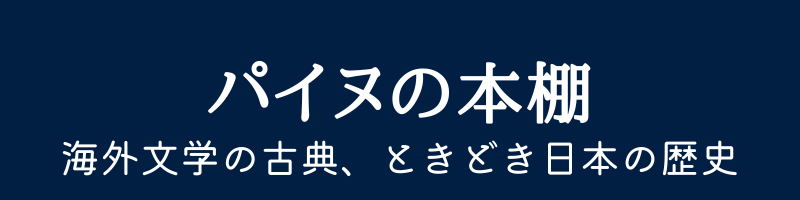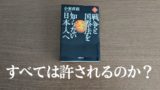TITLE : Heart of Darkness
AUTHOR : Joseph Conrad
YEAR : 1899
GENRE : Psychodrama

大密林がクルツにささやきかけたこと、それは彼自身が知らない自己の本性に関わること、そう、この地での大いなる孤独と語り合うまで 彼自身見当もつかなかったこと、だったのではなかろうか―しかもそのささやきは、抗いがたいほど魅惑的だった。彼のなかでそれが大きく谺したのは、もともと彼の内面がからっぽだったからだ
P149(『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著、高見浩訳、新潮社、2022年)
テーマ:文明の闇
【作品を読み解く3つのポイント】
1、植民地主義の実態
2、密林と狂気
3、The horror ! The horror !
【1】植民地主義の実態
「何百万もの無知蒙昧な人たちを、
おぞましい風習から救い出してあげなきゃ」
この物語の主人公マーロウの
「できた叔母」は、
コンゴ自由国へ派遣されることになった
甥っ子に対して、
このような、はなむけの言葉を送ります。
「しかし、あの会社の目的は
金儲けですからね」
マーロウはさりげなく切り返しますが、
そのような辛辣な皮肉にも、
彼女の抱く輝かしい理想の世界は
少しも揺らぐことがありません。
マーロウの叔母を魅了した理想は、
「植民地主義(colonialism)」
と呼ばれるもので、
現在では、非人道的な搾取と、
過激な人種差別をもってして知られる
人類のいわば「負の遺産」として
多くの人々に認識されています。
この2人の会話から、
大国による侵略と統治が、
その土地と、そこに住む原住民たちの
「近代化を促進する」という思想が
しごく当然のものとして、
当時のいわゆる「インテリ」たちの間で
共有されていたことがわかります。
ただ、この連中が話すのを聞いていると、下賤な海賊もいいところだった。無鉄砲なだけで度胸に欠け、貪欲なだけで大胆不敵な精神力のかけらもない。ひたすら残忍で真の勇気に欠けるんだ。(中略)頭にあるのは大地の奥ふところから財宝をむしりとることだけで、道徳的な目標の皆無な点は金庫破りの盗賊どもと選ぶところがない。
P78-79(『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著、高見浩訳、新潮社、2022年)
コンゴ自由国に到着したマーロウは、
そこで植民地の実態を目の当たりにします。
沖合から原住民の部落へ向けて
大砲で砲撃を加える軍艦。
無謀な鉄道建設のために
過酷な労働を強いられる現地の人々。
野心と欲望の塊と化した
「光の伝道者(Worker)」たち。
そんな植民地の実態を
もっとも如実に表しているのが、
アフリカにおける
「蛮人教化策の産物」ともいうべき
「順応した黒人」の存在です。
コンゴ自由国に到着したのちに、
勤務先となる中央出張所へ向かう途中、
マーロウは、
首枷と一本の鎖でつながれた黒人たちが
土を詰め込んだ小さな籠を頭にのせて、
縦一列に並んで小道を登ってくるところに
遭遇します。
やせ衰え、苦しげに坂道を進みながら、
「死んだように完璧な無関心さを」
保っている彼らとは対照的に、
その後ろから、つまらなそうに歩いて来る
軍服とライフルをまとった監視役の黒人は、
マーロウを見かけるなり、
同志の証としてニヤッと笑って見せます。
マーロウはこのとき、帝国と属国の間に潜む
理不尽を垣間見ると同時に、
彼がこれから知り合うことになる、
狡猾な「しょぼついた目の悪魔」の存在を
予感するのです。
人間ってやつは、ときどき愚かしいことを考えるものでね。静まり返った高い樹林は、不気味なくらい忍耐強くあの二人と対峙して、人間たちの途方もない侵入がすぎ去るのを黙然と待っていたよ。
P85(『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著、高見浩訳、新潮社、2022年)
マーロウの新天地となった商社の出張所は、
案の定、俗物たちの巣窟と化しており、
自分に課された職務と、
漠然とした出世に対する期待以外には、
ほとんどなにも持ち合わせていない
空虚な人間たちであふれていました。
さらに悪いことには、
彼らのほとんどが手持ち無沙汰なので、
同僚の陰口をたたいたり、
「愚かしい策謀」を仕掛けて
他人の足を引っ張ったり、
時には、原住民に対して
暴君のように振舞ったりして、
無益に時間をつぶしているのです。
そんな中央出張所の責任者である支配人は、
現地の気候に適応できる健康だけが取り柄の
「学問的な素養もなければ知性もない」
威張りくさった男で、
それにもかかわらず、接する相手を
「なんとも落ち着かない気分」にさせる
不気味な力を持っていると、
マーロウは指摘しています。
「一度も病に倒れなかった」おかげで
不動の地位を確立した支配人が、
憎々しい気持ちで見つめるのは、
この中央出張所から
川をさらに上流へ進んだところにある、
「奥地出張所」を管理する
クルツという謎の男です。
マーロウは、病に倒れ、
瀕死の状態に陥っている彼を救出すべく、
壊れて動かなくなった蒸気船を修理して、
いざ、奥地へと乗り出していきます。
【2】密林と狂気
肝心なのは、クルツが才能豊かな人物であり、中でも飛びぬけていた才能、掛け値なしに本物と思われた才能とは、語る能力、であり、言葉遣いの妙、だったということ。そう、胸中の思いを自在に表現し、人を幻惑し、啓蒙する、桁外れに熱狂的で、しかも卑しむべき能力、それは拍動する光の流れ、不可侵の闇の奥から流れ出る欺瞞に満ちた言葉の数々とも言えただろう。
P120(『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著、高見浩訳、新潮社、2022年)
マーロウは、クルツと対面するまでの間に
彼にまつわるさまざまな噂を耳にします。
「万能の天才」
「象牙を送ってよこしましたよ。大量にね」
「いかがわしい、愚劣な説教口」
クルツのことをよく思わない
支配人を中心に渦巻く陰謀の空気と、
奥地出張所における
目を見張るようなクルツの実績を傍目に、
マーロウは、
「何らかの道徳的な理想に燃えて
やってきたらしい」
クルツという男に対して、
徐々に興味をそそられるようになります。
「各出張所はより良き世界へ向かう
道標であるべきだ。」
「交易の中心であることは当然として、
同時に、人間性の向上と教化を目指す拠点で
なければならない」
以前、中央出張所で勤務していたクルツが
このように説教を垂れたので、
本当にうんざりしてしまったのだと、
支配人は、その支援者である叔父に
愚痴をこぼします。
ここからわかることは、
奥地出張所から「大量の象牙」を
出荷するようになったクルツは当初、
中央出張所の支配人をはじめとする、
「決まりきったルーティンを
無難にこなしているだけ」の
男たちとは違って、
「植民地主義」を華やかに飾り立てる
「啓蒙思想」に触発された
壮大な理想を抱いていたらしい、
ということです。
大密林は彼のなかに眠る野蛮な本能を目覚めさせ、かつて一度は満たしたこともある醜悪な欲望を思いださせることで、自らの無慈悲な胸に彼をかき抱こうとしている―おれにはそう思えたのさ。
P170(『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著、高見浩訳、新潮社、2022年)
危険と隣り合わせの航行をなんとか遂行した
マーロウとその一行は、
そこで奥地出張所の「異様な」実態を
目の当たりにすることになります。
彼らを出迎えた
「まだら模様の道化服」の男は
マーロウに対して、
自分がここへやって来た経緯と、
クルツとの出会いについて語ります。
これにより判明したのは、
かつて、偉大なる啓蒙思想家であり、
類まれなる演説家でもあった男は
現在では、この奥地出張所で、
目的を達成するためなら手段を選ばない
残忍極まる「象牙の王」として君臨している
という事実でした。
クルツにいったいなにが起ったのか?
病にむしばまれ、皮と骨だけになり、
衰弱しきったクルツの口から
多くが語られることはありませんでしたが、
コンゴ河を取り巻く熱帯のジャングルと、
クルツに対する「まだらの男」の陶酔ぶり、
そして、クルツ自身が記した
「蛮習廃止国際協会」への報告書から、
マーロウは、クルツの身に起きた
予期せぬ事態を推察します。
【3】The horror ! The horror !
真夜中を過ぎて、マーロウが目を覚ますと、
蒸気船からクルツの姿が消えていることに
気がつきます。
担架で担ぎ込まれたはずのクルツが
どうやって脱走したのかもわからぬまま、
「漠然とした恐怖」を感じつつも、
マーロウはクルツの跡を追いかけます。
夜の森の奥でクルツを発見したマーロウは、
ふらつきながら立っている彼の視線の先に、
かがり火と、太鼓の響きと、
「奇怪な呪文の唱和」を目撃します。
『おれにはな、遠大な計画があったんだ』
『あと一息で偉大な事業を
成就できたところを』
原住民たちの祭祀(儀式?)を
未練がましいまなざしで見つめながら、
そうつぶやいたクルツの声音に、
マーロウは彼の本性を垣間見たのでした。
「大密林の中にたった一人でいるうちに、
彼の魂は自らの内奥を見つめつづけて、
あろうことか!狂ってしまったんだろう。」
言い知れぬ恐怖にとらわれながらも、
その場からなんとかクルツを担ぎ出して、
船内へと連れ帰ります。
船が奥地出張所をあとにして程なく、
クルツは「激しい絶望の色」を浮かべながら
そっと息を引き取ります。
その死の間際に、
「願望と憎悪の奇妙な混沌」のうごめく
自身の「心の闇」を見つめ、
彼を包含する全宇宙に対して、
「地獄だ!」と審判を下したクルツ。
そんなクルツの苦痛に満ちた葛藤を
ある種の畏怖の念とともに
胸に焼きつけたマーロウは、
彼から託された遺品を携えて、
「墓場のような都市」(本社の所在地)に
舞い戻ったのでした。
大地は見慣れた大地ではなく、そこで暮らす人間は―まあ、人間らしくないわけではなかった。そこなんだ、そこが始末におえない点だった―あの連中も、人間でなくはないと思える点がね。それがしだいにわかってくる。(中略)だが、慄然とするのは、そんな彼らもおれたちと同じ人間なんだという考えが浮かぶときでね―そうなんだ、自分もまた、この荒々しい狂騒とどこかでつながっていると感じるときさ。
P93(『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著、高見浩訳、新潮社、2022年)
本作『闇の奥』を改めて読んでみて、
個人的に特に興味深いと感じるのは、
シンボルを用いた「暗示」の効果です。
この文庫本に収録されている
訳者・高見浩による解説のなかで、
「コンラッドの分身であるマーロウは、
大英帝国の植民地、その統治だけは
手放しで礼賛しているのである。」(P228)
と指摘しているのですが、
私パイヌの個人的な考察としては、
作者コンラッドは、大英帝国の植民地政策を
手放しで礼賛しているのではなく、
本作『闇の奥』を執筆した際には、
むしろ、そのような政策に対して、
批判的な考えを持っていたのではないか?
と考えています。
というのも、本作の冒頭の場面で、
マーロウをはじめとする乗組員たちが
テムズ川に浮かぶ船の上で
沖へ向かうために
引き潮を待っている様子というのが
描かれているのですが、
このなかで、以下のような言及が
記されているのです。
上流のグレイヴゼンドの町の上空はすでに薄暗く、さらにその奥の空は暗くにごって、地上最大にして最も偉大な街の上に低くたれこめていた。
P9(『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著、高見浩訳、新潮社、2022年)
ここにある
「地上最大にして最も偉大な街」とは、
「ロンドン」のことを指しているとのこと。
このことから、
冒頭の場面で、マーロウたちが停留している
テムズ川の下流と、
そこからはるか奥へ
川をさかのぼったところに位置する
ロンドンの街が、
マーロウが派遣された
コンゴ河沿岸の中央出張所と、
そのさらに上流に位置する奥地出張所の
関係性を彷彿させるといえるのです。
ロンドンの街と
クルツの奥地出張所のイメージが、
象徴的な意味において、
「重ねられている」と考えるのは、
やや強引なとらえ方になるでしょうか?
ともあれ、クルツに代表される
帝国の表の顔と裏の顔というのは、
古今東西の、どの例を取り出してみても、
ほとんど「同じ顔」をしているということは
はっきりと指摘することができそうです。