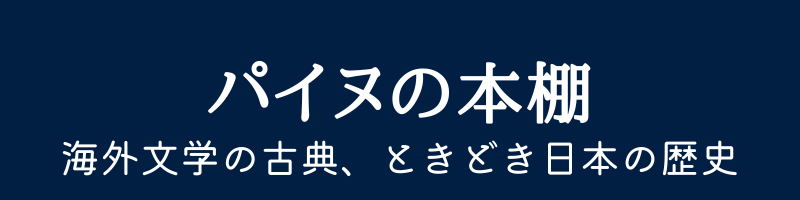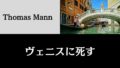TITLE : The Seagull
AUTHOR : Anton Chekhov
YEAR : 1896
GENRE : Comedy, Avantgarde Theatre

舞台に立とうが物を書こうが同じこと、私たちの仕事で大事なのは、名声だとか栄光だとか、私が夢見ていたものではなく、耐えることができるかどうかなの。十字架を背負って歩みながら、自分のやっていることを信じきれるかどうかなの。
P145(『かもめ』アントン・チェーホフ著、浦雅春訳、岩波書店、2010年)
テーマ:鳥瞰的視点
【作品を読み解く3つのポイント】
1、新しい演劇
2、生きた人間
3、「かもめ」の正体
【1】新しい演劇
「動きのない」芝居。
劇的な出来事もなければ、
明快なメッセージもない。
視覚的な変化に乏しいからこそ、
ますます難解な印象を受けます。
とはいえ、本作『かもめ』は、
当時のロシアの文壇が直面していた
文学的なテーマの行き詰まりや、
作者自身が抱えていた作家としての課題を
見事に突破したという意味において、
記念すべき作品でもあるといえます。
その目新しさは
作品の随所に見出すことができますが、
今回注目したいのは、
「演じることを演じる『メタ演劇』」
という特徴です。
あれは、やれ新しい形式だ、芸術における新時代の幕開けだという高飛車な物言いじゃない。私に言わせりゃ、あそこに新しい形式なんてありません。あるのはたちのわるい冗談だけ。
P32-33(『かもめ』アントン・チェーホフ著、浦雅春訳、岩波書店、2010年)
第一幕のなかで、青年トレープレフは、
自身が演出した前衛的な芝居を
観客たち(特に母親)から
酷評されてしまいます。
『かもめ』の初演時には、
まさしくこの場面で、
客席に大失笑が巻き起こった
といいますから、
このような予期せぬ反応は、
トレープレフにとっても、
作者チェーホフにとっても、
皮肉以外のなにものでもありません。
ただ、ここで興味深いのは、
このトレープレフというキャラクターを
「新しい演劇」の模索に苦心していた
チェーホフ自身の分身としてとらえれば、
彼の芝居は失敗したかのように見えて、
実は、その場にいる観客をも巻き込んだ
大がかりな「メタ演劇」の演出に
成功していたとも考えられるのです。
要するに、トレープレフが演出した
斬新すぎる芝居を理解できない
登場人物たちが示した否定的な反応を、
チェーホフが披露した新しい演劇を
理解することができなかった
初演時の観客の「失笑」として、
「再現」することによって、
劇場全体を、マトリョーシカ人形のような
巨大なフラクタル構造のなかに
組み込んでしまったというわけです。
【2】生きた人間
あなたのお芝居って、演りにくいわ。生きた人間が出てこないんですもの。
P21(『かもめ』アントン・チェーホフ著、浦雅春訳、岩波書店、2010年)
先ほど言及した、劇中劇の効果に加えて、
登場人物たちに与えられたセリフからも
本作の「メタ的(超越的)要素」を
強く意識させられます。
その最たるものと思われるのは、
「生きた人間が出てこない」
というセリフです。
このセリフは、物語のなかで2度も、
しかも、ほぼ同じ言い回しで
用いられています。
一つ目は、上の引用部にある
トレープレフの恋人ニーナのセリフです。
もう一つは、彼の母親の愛人でもあり、
のちに、彼からニーナを奪うことにもなる
売れっ子作家トリゴーリンのセリフです。
トレープレフ自身の母親を除けば、
この2人の登場人物こそ、
彼のプライドを傷つけ、
その敗北感を増幅させた
張本人でもありました。
「中心の喪失」、それにともなう「主人公中心主義」からの脱却―戯曲におけるその最初の試みこそ『かもめ』であった。
P180(『かもめ』アントン・チェーホフ著、浦雅春訳、岩波書店、2010年)
「生きた人間が出てこない」
これはなにも、
トレープレフの芝居にかぎったことでは
ありません。
なにを隠そう、この『かもめ』にも、
その特徴が顕著に現れている
といえるのです。
その原因の一つには、
2つ目の引用部にもあるとおり、
本作に、特定の主人公が存在しないことが
挙げられます。
えっ、主人公はトレープレフじゃないの?
と思われた方もいるかもしれません。
確かに、先ほど【1】のところでは、
トレープレフを、チェーホフの分身として
説明しましたが、
実のところ、このトレープレフ以外の
登場人物についても、同じことが言えます。
極論すれば、登場人物は全員、
チェーホフの分身であり、かつ、
主人公でもあるのです。
この芝居に出てくる人間は、誰も彼も、
チェーホフの分身なのですから、
「生きた人間が出てこない」のも
当然と言えば当然のことです。
もちろん、作者の分身だけが
物語の主人公になり得る
というわけではないのですが、
このように「メタ構造」の効果を利用して、
作者自身のさまざまな顔(内面の複雑さ)を
表現するという手法は、
非常に斬新な演出であるといえるでしょう。
【3】「かもめ」の正体
私は、かもめ……。いいえ、そうじゃない。(額をぬぐう)何を言っているのかしら、私?
P140(『かもめ』アントン・チェーホフ著、浦雅春訳、岩波書店、2010年)
「かもめ」というタイトルは、
その物語の内容に負けず劣らず
意味深長です。
では、この「かもめ」とは、
いったいなにを表しているのでしょうか。
「かもめ」という言葉は、
トレープレフとニーナの間において
とりわけ重要な意味を持っているようです。
2人のセリフに秘められた意味を
推測すると、
「かもめ」とは、彼らの「イノセンス」を
象徴しているのではないか?
ということが考えられます。
お互いに夢を抱いて語り合う場面と、
それぞれに夢破れたあとで
言葉を交わす場面では、
「かもめ」という言葉が与える印象が、
大きく変化してしまっていることが
わかります。
さらに、物語の終盤では、
トレープレフが撃ち落としたかもめが
剥製になっていることから、
彼らが持ち合わせていた純粋さが、
その形はかろうじて残っていても、
もはや生命のないものへ成り果てたことが
暗示されているのです。
ちなみに、このかもめを
剥製にするように注文したのは、
作家トリゴーリンとのことです。
(本人は、身に覚えがないらしい。)
このトリゴーリンにも、
作者チェーホフの分身としての役割が
与えられているのだとしたら、
トレープレフやニーナが持ち合わせていた
創作や演劇に対する純粋な情熱が、
彼にはすでに失われてしまったことを
暗示しているのかもしれません。
このように考えていくと、
『かもめ』という戯曲のタイトルには、
なんだか冷やりとするような
自虐めいた響きを感じてしまいます。