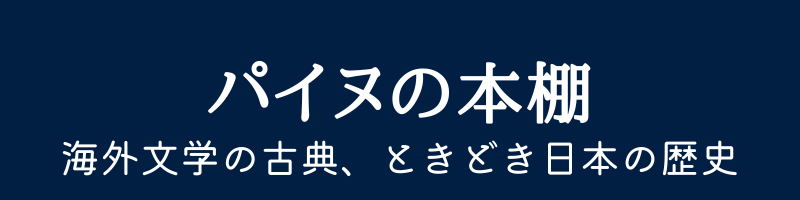TITLE : The Old Man and the Sea
AUTHOR : Ernest Hemingway
YEAR : 1952
GENRE : Nautical Fiction

しかし、おれは、人間ってものがどんなことをやってのけられるかを、やつにわからせてやるんだ、人間が耐えていかねばならないものを教えてやるんだ。
P59(『老人と海』アーネスト・ヘミングウェイ著、福田恆存訳、新潮社、1966年)
テーマ:人間の限界
【作品を読み解く3つのポイント】
1、落ちぶれた漁師
2、2つの闘い
3、骨になった大魚
※本記事の商品リンクには、
高見浩訳(新潮文庫)を掲載していますが、
記事の本文で引用するのは、
福田恆存訳(新潮文庫)のものです。
【1】落ちぶれた漁師
『老人と海』の創作背景については、
『ヘミングウェイ全短編3』(新潮文庫)
に収録されている
翻訳者の解説が非常に参考になります。
ヘミングウェイの「キューバ時代」と、
その当時の作品群を振り返るなかで、
本作については次のような言及があります。
残された作品から判断する限り、彼の文学は第二次大戦の終了以降、長い下り坂にさしかかっていたと見ていいだろう。短編は質量共に二十代、三十代の頃とは比べるべくもないし、長編にしても、生前発表されたものの中では、わずかに『老人と海』が光っているにすぎない。それは巨きな落日の最後の光芒でもあったのだろうか。
P696-697(『蝶々と戦車・何を見ても何かを思いだす―ヘミングウェイ全短編3―』高見浩訳、新潮社、1997年)
私パイヌの、一読者の感想としても、
翻訳者・高見浩の指摘には、
そうだったのか!という驚きとともに、
なるほど!という大きな共感を覚えます。
物語のなかで、徹底して描かれる
「敗者」としての老人の姿は、
ヘミングウェイの作家としての限界を
投影しているようにもみえます。
2か月以上も不漁が続いた老人と、
創作力の低下が顕著になってきた作家に、
「皮肉な共通点」を見出した読者も
きっと多いことでしょう。
きっときょうこそは。とにかく、毎日が新しい日なんだ。
P27(『老人と海』アーネスト・ヘミングウェイ著、福田恆存訳、新潮社、1966年)
一匹も釣れなくなってから
85日目を迎えたその日も、
老人はまだ希望を捨ててはいませんでした。
若い頃にくらべれば、確かに、
腕は落ちてしまったかもしれない。
しかしその眼には、依然として、
不屈の精神がみなぎっていたのです。
自信を取り戻すという決意はもとより、
周囲の評判を覆すという意味においても、
今回の漁(あるいは作品)には、
老人(あるいは作者)の
相当な覚悟がうかがえます。
【2】2つの闘い
さあ、殺せ、どっちがどっちを殺そうとかまうこたない。
P84(『老人と海』アーネスト・ヘミングウェイ著、福田恆存訳、新潮社、1966年)
3日間ほぼ不眠不休で漁にあたった老人は、
海上で2つの激闘を繰り広げました。
一つは、大捕り物となった
カジキとの闘いです。
不漁85日目の昼、待ちに待った大物が
ワナにかかります。
ここから、昼夜問わずの
生死を賭けた綱引きがはじまり、
その翌々日の朝になって、
老人はようやく獲物を手に入れます。
もう一つは、サメとの闘いです。
いざ帰港しようとする老人の前に、
その獲物を横取りしようと現れた
何十匹ものサメが立ちはだかります。
血の匂いを嗅ぎつけて
老人の船のそばに群がると、
続けざまに四方八方から噛みついて
カジキの肉を奪い去っていきます。
いいことは長続きしないものだ、とかれは思った。これが夢だったらよかったのに、いまとなってはそう思う、魚なんか釣れないほうがよかった。
P93(『老人と海』アーネスト・ヘミングウェイ著、福田恆存訳、新潮社、1966年)
命からがら港へたどり着いた頃には、
せっかく手に入れた大物も、
見るも無残な有様となっていました。
18フィート(約5.5メートル)もある大魚は
ほとんど骨と化していたのです。
最後の場面では、
港を偶然訪れた観光客が
このカジキの骨を目の当たりにして
サメのものと勘違いする様子が描かれます。
老人の孤独な闘い。
食い荒らされた大魚の残骸。
そこへふらりと現れる
観光客の薄っぺらな関心。
84日間の不遇と、3日間の死闘の末に、
ようやく勝利を手にした老人は、
海から陸へ帰還するたった数時間のうちに、
再びもとの敗者の姿へと
引き戻されてしまうのでした。
【3】骨になった大魚
打ちのめされるというのも気楽なものだな、とかれは思う、こんなに気楽なものとは知らなかった。それにしても、お前を打ちのめしたものはなんだ。
P110(『老人と海』アーネスト・ヘミングウェイ著、福田恆存訳、新潮社、1966年)
なぜ、大魚は骨になってしまったのか?
そのシンボルとしての意味について、
少しだけ考察してみようと思います。
まず一つには、冒頭でも言及したように、
ヘミングウェイの作家としての限界を
暗示しているのではないか?
ということが考えられます。
老人=ヘミングウェイ
大魚=創作力、作品そのもの
サメ=世間の評判(酷評)
このように置き換えてみると、
物語の裏側に潜む作家の苦悩が
まざまざと浮かび上がってきます。
その一方で、
もう少し楽観的な見方をするのであれば、
大魚の骨を、老人の「復活」のしるしとして
とらえることもできるかもしれません。
ちなみに、カジキについては、
その尻尾を「大きな鎌」と呼んで
くりかえし表現していることから、
「大魚=死神」という
メタファーとしての意味を
指摘することができそうです。
※死神は、よく大鎌を携えた姿で描かれる。
すると、どうでしょう?
大魚に打ち勝つことによって、老人は、
その身に忍び寄る「死の気配」を払拭し、
また、港へ無事生還することで、
少年や漁師仲間たちの前に、文字どおり、
「よみがえった」ことになります。
このほかにも、漁の間に老人が見た
「ライオンの夢」の象徴というのも
実に興味深いうえに、
同じ海洋小説(漁師と大魚の話)の
つながりで、
メルヴィルの『白鯨』との関連性も
気になるところですが、
話が長くなってしまうので、
今回はここまでということで。