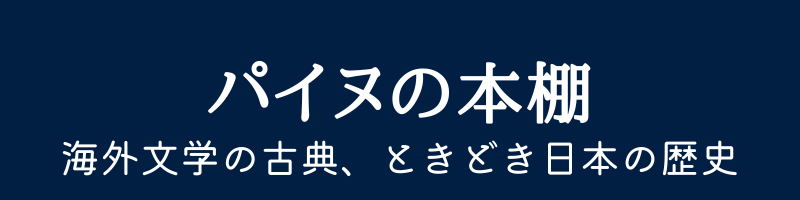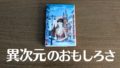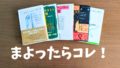TITLE : The Great Gatsby
AUTHOR : F. Scott Fitzgerald
YEAR : 1925
GENRE : Love Story

ここまで来たら、ほんの少しで夢に手が届きそうで、つかみ損なうことがあるとは考えなかったろう。夢が後ろにあるとは思いもよらなかった。もう夢は、都会の向こうに広がる巨大な闇、この国の暗い原野がうねって続く夜の世界へ行っている。
P295(『グレート・ギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド著、小川高義訳、光文社、2009年)
テーマ:アメリカン・ドリームの終焉
【作品を読み解く4つのポイント】
1、ジャズエイジ
2、過去から来た恋人
3、代弁者たち
4、エクルバーグ博士の眼鏡
【1】ジャズエイジ
本作の舞台となった1920年代のアメリカは
「狂乱/狂騒の時代」と呼ばれたり、
あるいは、フィッツジェラルド自身の
作品にちなんで
「ジャズエイジ」と呼ばれたりもします。
第一次世界大戦の勃発にともなう
軍事的・経済的需要の高まりを受けて、
ヨーロッパに対する輸出を拡大させた結果、
債務国から債権国へと変貌を遂げたことで、
この当時のアメリカ社会は、
かつてない好景気を迎えました。
それ以前には、
「金ぴか時代(ギルディッド・エイジ)」
と呼ばれた時代がありました。
1865年に終結した南北戦争以降、
工業化の促進と西部の開拓によって
急激な経済成長を遂げた一方で、
こうした資本主義の台頭の陰では、
拝金主義や政治の腐敗、貧富の格差
といったものが蔓延したといいます。
財産があれば、青春と神秘をつかまえて保存しておける。着替える衣装が多ければ颯爽としていられる。そしてデイジーは、銀のように艶めいて、あくせく働く庶民階級の上に超然としていられる。
P244(『グレート・ギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド著、小川高義訳、光文社、2009年)
ノースダコタの貧しい農家出身の
ジェイムズ・ギャッツ青年は、
「ジャズエイジ」とも「金ぴか時代」とも
ほとんど無縁の存在でしたが、
子どもの時分から途方もない空想家で、
自分はいつの日か必ず大成するものと
信じて疑わない野心的な男でもありました。
鬱屈とした日々を送っていた青年は
ある日、スペリオル湖の岸辺で、
アメリカン・ドリームを実現した
西部開拓時代の生き残りでもあった
ダン・コディという男に出会い、
「世界の栄華」を目の当たりにします。
コディと親しくなった青年は
「ジェイ・ギャツビー」と名前を改め、
彼とともに故郷の中西部を離れます。
それから紆余曲折を経て、
ヨーロッパの戦場へ出征を控える
中尉となったギャツビーは、
南部の良家の「お嬢さん」であった
デイジーと出会い、恋に落ちます。
ギャツビーは、コディとの出会いによって、
「偉大なる事業」を成し遂げることに
人生を捧げようと一度は決心したものの、
のちに、デイジーと出会うことによって、
「愛する人」を手に入れるために
生命を捧げようと決意するのです。
【2】過去から来た恋人
ギャツビーが帰還したときには、
永遠の愛を約束したはずのデイジーは
すでに、トム・ブキャナンという裕福な男と
結婚していました。
そのような恋人の裏切りにあっても
ギャツビーの情熱が冷めることはなく、
彼女の愛を取り戻すために、
あらゆる手段を尽くして
大富豪の地位へのし上がります。
デイジーとトムが、
シカゴからニューヨークへ出てきて
ロングアイランドのイーストエッグに
落ち着いたあと、
対岸のウェストエッグに邸宅を構えた
ギャツビーは、
週末ごとに盛大なパーティを開催しながら、
デイジーの帰りを今か今かと待ち続けます。
デイジーからしてみれば、数年の時を経て、
再び彼女の前に姿を現わしたギャツビーは
まさに「過去から来た恋人」でした。
愛人がらみの問題で、夫との関係が
すっかり冷え込んでいた彼女にとって、
元カレとの思いがけない再会は、
願ってもない幸運が舞い込んだようなもの
だったのかもしれません。
「過去を繰り返すことはできない」
P179(『グレート・ギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド著、小川高義訳、光文社、2009年)
「できない?」ギャッツビーには心外のようだ。「できるに決まってるじゃないか!」
そう言って、あたりを見やる。つかみそこなった過去が、まだ遠くへは行かず屋敷の陰にひそんでいるとでもいうのだろうか。
ギャツビーの存在は、デイジーに
麗しく華やかな彼女自身の娘時代を
思い出させたことでしょう。
それと同時に、彼の方へすり寄ることで、
不倫をしている夫に対して、
「浮気」という形を使って
対抗することもできたのです。
ギャツビーは、デイジーが
自分の元へ戻ってきてくれたものと
すっかり思い込み、
彼女に離婚を迫りますが、
デイジーには、現在の贅沢三昧な暮らしを
手放す気などさらさらなく、
ギャツビーの「夢」はもろくも崩れ去り、
結果として、割に合わないほどの
「高い代償」を払わされることと
なりました。
朝日の訪れによって、
夜の黒いベールをはぎ取られていくように、
ギャツビーの栄華は幻影となって、
唐突にふっと消え失せてしまうのでした。
【3】代弁者たち
本作の人物造型や舞台装置には、
「夢追い人・ギャツビーの悲劇」という
ストーリーの内容以上に
興味をそそられるものがあります。
その一例としてはまず、
登場人物たちのバックグラウンドが
挙げられます。
下の引用部にもあるように、
この物語の主要キャストは皆、
西部からやって来た人々であることが
強調されていて、彼らは、
かつてイギリスの植民地が置かれていた
13の州をはじめとする東部とは、
異なる背景を持つ人間であることが
わかります。
ちなみに本作では、西部は西部でも、
現在アメリカの地理的な区分として
認識されている西部ではなく、
「東部13州以外の場所」という意味で
「西部」という言葉が使われていて、
厳密に言えば、ニックもトムもギャツビーも
「中西部」の人間であり、
デイジーとジョーダンにいたっては
「南部」の出身ということになります。
作者フィッツジェラルド自身も
ミネソタ州出身ということなので、
主要キャストの男性陣と同じ
「中西部」の人間であることがわかります。
いま思うと、ここまで語ってきたのは西部の物語だ。要するに、トムもギャッツビーもデイジーもジョーダンも私も、みな西部人なのである。たぶん何かしらの困った共通点があって、東部の生活とは微妙にずれていた。
P287(『グレート・ギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド著、小川高義訳、光文社、2009年)
それからもう一つ、
登場人物たちのバックグランドについて
指摘しておきたいのが、
「移民としてのルーツ」という点です。
「移民の国アメリカ」には、
コロンブスの時代より
(一説にはヴァイキングの時代とも)
さまざまな慣習・文化を持った人々が
世界各国からやって来て
一つの国を作り上げてきました。
現在でも「〇〇系アメリカ人」という言葉で
その人のルーツが説明されることが
ありますが、
国としての歴史が比較的浅い分、
それぞれのバックグランドが
その人の人格に与える影響というのも
それだけ大きいということがわかります。
本作の主要キャストについても
やはり同じことが言えて、
それぞれのルーツに関する特徴が、
各キャラクターの人物造型にも
少なからず影響しているということは、
アメリカ文学史のテキスト等でも
よく指摘されていることで、
この点を分析してみると
非常に興味深いものが見えてくるのです。
Wikipediaの説明と、
いくつかのネットの情報を参考に、
主要キャストのルーツを分類してみると、
次のようになります。
【スコットランド系】
ニック、トム、ウィルソン(車屋の店主)
【アイルランド系】
デイジー
【イングランド系】
ジョーダン
【ドイツ系】
ギャツビー
このようにして見てみると、
本作の主要な登場人物たちは、その多くを
「スコットランド系アメリカ人」が
占めているということがわかります。
物語の冒頭部分で、語り手のニックと、
トムと、デイジーと、ジョーダンが
イーストエッグのブキャナン邸で
ディナーをともにする場面がありますが、
会食のあとの懇談で、
トムが「文明と人種」にまつわる
大演説を打ちながら、
「われわれは北ヨーロッパの系統なんだ。」
と主張したあとで、
「刹那の迷い」を見せながらも
わずかにうなずいて、
妻デイジーも「同類」として認めています。
一見すると、本筋とは
ほとんど関係がないようにも思える場面
なのですが、
「バックグラウンド」という観点から
この場面を考察してみると、
スコットランド人とアイルランド人の
「軋轢」のようなものが見えてくるのです。
入れ替わりに見えてくるように思えたのが、かつてオランダ人水夫の眼前に花開いた島だった。みずみずしい緑の新世界が、ここまで張り出していた。
P294(『グレート・ギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド著、小川高義訳、光文社、2009年)
このようなバックグランドの問題を通して、
作者フィッツジェラルドが
いったいなにを伝えようとしていたのか?
ということについては、
さまざまな解釈ができると思います。
しかし、この問題については、実のところ、
当事者にしかわからない
センシティブな事柄でもあると思うので、
よほどこのような事情に
精通している人物でもない限り、
分析することはむずかしいのではないか?
とも感じています。
とはいえ、さまざまなルーツのなかでも
とりわけ、スコットランド系と
アイルランド系の人々が、
アメリカ合衆国の建国に関して
多大なる影響を与えたということは
歴史的な事実として知られています。
その証拠に、といってはなんですが、
アメリカ合衆国の国歌「星条旗」の作者は
フランシス・スコット・キーという詩人で、
その名前から推察するに、おそらく
アイルランド、またはスコットランドに
ルーツを持つ人物であることがわかります。
彼の子孫には、なにを隠そう、
本作『グレート・ギャツビー』の作者である
フランシス・スコット・フィッツジェラルド
がいるということですから、
彼自身もまた、自分のルーツから
強い影響を受けていたということは
どうやら間違いなさそうです。
【4】エクルバーグ博士の眼鏡
本筋とは別のところで、
ストーリーの展開を左右する
重要なキーを与えられているのが、
「T・J・エクルバーグ博士の眼鏡」です。
トムの愛人マートルが、
自動車店を営む夫とともに暮らしている
「灰の谷」は、
大都会ニューヨークと、
ブキャナン夫婦やギャツビーが暮らす
高級住宅地との間に横たわる
ゴミの掃き溜めのような場所であることが
語られています。
「T・J・エクルバーグ博士の眼鏡」は
この「灰の谷」に打ち捨てられた
元眼鏡屋の看板として登場するのですが、
下の引用部の内容からもわかるとおり、
「T・J・エクルバーグ博士の眼鏡」には
「神の目」としての役割が与えられていると
指摘することができるのです。
ウィルソンの視線の先には「T・J・エクルバーグ博士の目」があったのだ。ぼやけた大きな看板の目が、ほどけていく闇の奥から、ぬっと現れていた。
P260-261(『グレート・ギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド著、小川高義訳、光文社、2009年)
「神の目はごまかせねえ」
しかし、ここのところで一つ、
素朴な疑問が湧いてきます。
「神の目」を持つ
T・J・エクルバーグ博士はなぜ、
「眼鏡をかけている」のでしょうか?
アメリカの1ドル紙幣にも印刷されている
いわゆる「プロヴィデンスの目」が、
「万物を見通す目」や「神の全能の目」
と言われているように、
「神の目」は、この宇宙全体における
森羅万象を把握する圧倒的な視野を持った
偉大なる「目」なのです。
神様は、裸眼のままで、
万物を見通すことができるはずなのに、
「灰の谷」の「神の目」は
どうして眼鏡をかけているのか?
ということが、
個人的には、どうにもひっかかるのです。
「T・J・エクルバーグ博士の眼鏡」は
「灰の谷」に適応するための
「防塵メガネ」のようなものであるとも
考えられますが、
やはり、視力の低下に対応するための
「遠視または近視用の眼鏡」と考えるのが
妥当でしょう。
フィッツジェラルドはヘミングウェイと同じ
「ロストジェネレーション」と呼ばれる
当時の若手作家にあたるわけですが、
彼らが「神を見失った(lost)」ように、
神様の方でもまた、
戦争に明け暮れる人間たちを教え諭す術を
見失ってしまったのかもしれません。