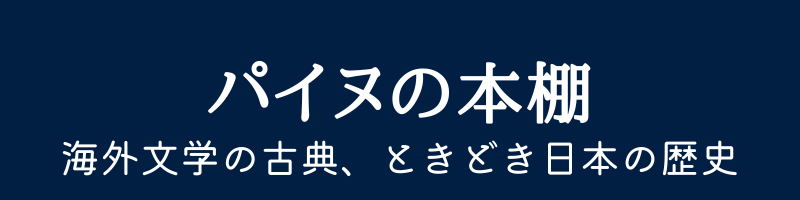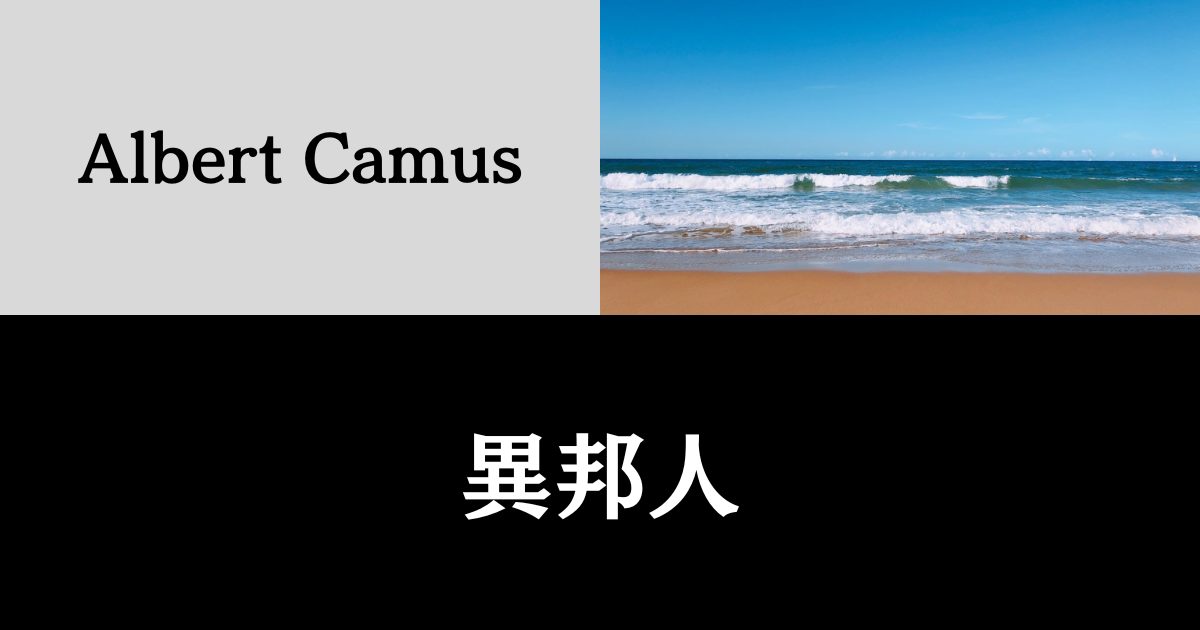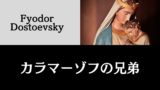TITLE : L’Étranger
AUTHOR : Albert Camus
YEAR : 1942
GENRE : “Theatre of the Absurd”

他人の死、母の愛―そんなものが何だろう。いわゆる神、ひとびとの選びとる生活、ひとびとの選ぶ宿命―そんなものに何の意味があろう。
P125(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
テーマ:常識という理不尽
【作品を読み解く3つのポイント】
1、偶然と不運
2、それは太陽のせいだ
3、怒りと解放
【1】偶然と不運
「それなら、なぜこの男は武器をたずさえていたのか。なぜ、正にあの場所へもどったのでしょうか?」それは偶然だ、と私はいった。
P91(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
「それは、なにものも意味していない」
「それは、どちらでも同じことだ」
主人公ムルソーは、折に触れて、
このように主張します。
それは一見して、彼の厭世的な態度を
表明しているようにも思えます。
しかしそれが、単なる主観などではなくて、
一つの事実を提示していたとしたら
どうでしょう?
眠いから、眠る。
海で泳ぎたいから、泳ぎにいく。
女の子とデートしたいから、デートする。
ムルソーの取った行動というのは、
誰しもが普通に行っていることであって、
それ自体には、なんら異常な点は
見られません。
ただ一つ、
「タイミング」という点を除いて。
予審判事側は、ママンの埋葬の日に、私が「感動を示さなかった」ことを、知っていた。
P67(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
人をあやめたムルソーは、
罪人として裁判にかけられます。
彼はなぜ、事件を起こしたのか?
法廷の場で、いよいよ事件の動機が
追及されるのかと思いきや、
審理は思わぬ方向へ転がりはじめます。
ムルソーが、いかに冷酷な男であるかを
立証しようとする検事は、
彼の母親の葬儀に立ち会った人々から
証言を引き出します。
彼は母親を養老院へ入れたが、
母親自身はそれを嫌がっていた。
彼は埋葬の際に、涙を見せなかった。
「煙草を吸った、よく眠った、
ミルク・コーヒーを飲んだ」
これに対して、ムルソーの弁護士は、
検事が証拠として提示したこれらの証言が、
今回の事件の動機とは、直接的には
関連するものではないことを指摘します。
「要するに、彼は母親を埋葬したことで告発されたのでしょうか、それとも一人の男を殺害したことで告発されたのでしょうか?」
P100(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
ところが、弁護士や擁護者の奮闘もむなしく、
ムルソーには極刑が言い渡されることに
なります。
奇しくも翌日には、この同じ法廷で、
別人の「親殺し」の審判が控えていました。
このような「偶然」が、
彼の印象をはからずも悪化させたことは
間違いありません。
ここへきて、またしてもムルソーは、
「タイミング」によって
人の道を外れることになったのです。
もし、犯行の当日の天候が、
曇りや雨だったとしたら?
もし、この裁判が、
真冬に開始されていたとしたら?
もし、ムルソーの審判の翌日に、
別人の親殺しの裁判が
予定されていなかったとしたら?
この事件に、多少なりとも
外的な要因が存在していたのだとしたら、
ムルソーが主張した「偶然」の可能性を
頭ごなしに否定することは、
本当に正当だといえるでしょうか。
【2】それは太陽のせいだ
焼けつくような光に堪えかねて、私は一歩前に踏み出した。私はそれがばかげたことだと知っていたし、一歩体をうつしたところで、太陽からのがれられないことも、わかっていた。
P62-63(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
裁判長から犯行の動機を尋ねられた
ムルソーは、
「それは太陽のせいだ」と答えます。
そんなことはありえない。
ムルソーの主張は支離滅裂だ。
そう感じた人も、きっと多いはずです。
そもそも「太陽のせい」とはいったい、
なにを示唆しているのでしょうか。
太陽が原因で、人をあやめる。
そんなことが、
本当にあり得るのでしょうか。
いよいよ暑さは上っていた。部屋のなかで傍聴人が新聞で風を入れているのが見え、皺苦茶の紙のたてる、小さな音が、絶え間なく続いていた。
P90(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
この小説は、
2つの大きな謎をはらんでいます。
まず一つには、
ムルソーの犯行の動機が不明なこと。
そしてもう一つは、法廷の審理が
彼の動機を明らかにしないことです。
ムルソーの主張を
そのまま受け取るのであれば、
彼自身には、端から
被害者を手にかける理由などなかった
ということになります。
ではなぜ、彼は人をあやめたのでしょうか。
一方で、ムルソーの凶悪さを証明しようと
躍起になる検事は、
ムルソーが、
「精神的に母を殺害した男」であることを
やたらと強調します。
しかし、ムルソーの母親の件は、
彼の弁護士が反論したように、
事件には直接関わりのないことです。
ではなぜ法廷は、事件の真相を
追及しようとしないのでしょうか。
この2つの謎については
さまざまな解釈ができそうですが、
私パイヌの個人的な考察としては、
単に、猛烈な暑さが影響したのではないか?
と考えています。
浜辺の焼けつくような日差しが
ムルソーの犯行を誘発し、
法廷の息詰まるような熱気が、
居合わせた人々の冷静な判断力を奪った。
要するに、
「太陽のせい」で人をあやめた男は、
酷暑のために「死」を宣告されたのです。
【3】怒りと解放
あの大きな憤怒が、私の罪を洗い清め、希望をすべて空にしてしまったかのように、このしるしと星々とに満ちた夜を前にして、私ははじめて、世界の優しい無関心に、心をひらいた。
P127(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
「学業を放棄せねばならなくなったとき、
そうしたものは、いっさい、
実際無意味だということを、
じきに悟ったのだ。」
ムルソーの、このセリフからは、
かつて彼を苦しめたと思われる、
深い絶望の痕跡を見て取ることができます。
経済的な理由だったのか、
健康面の問題だったのか、
その経緯を知る手がかりとなるものは
特に明記されていません。
「それは、なにものも意味していない」
「それは、どちらでも同じことだ」
このように強調する、その頑なな態度には、
「不感無覚」な彼の深奥に潜む
抑圧された怒りが
投影されていたのかもしれません。
私はかつて正しかったし、今もなお正しい。
P125(『異邦人』アルベール・カミュ著、窪田啓作訳、新潮社、1954年)
神、希望、来世、祈り。
篤い信仰心でもって、
彼を説き伏せようとする司祭に、
とうとうムルソーの怒りが爆発します。
これをきっかけに、自己完結に満ちた
彼の哲学的な思想が展開されるわけですが、
難解な部分も多いので、
私パイヌの理解力では、正直なところ、
手に余るものがあります。
とはいえ、
「死に近づいて、解放を感じる」という
ムルソーの最後の悟りには、
「常識」という名の
見えざる手枷足枷を意識させると同時に、
そのような束縛の「理不尽さ」を告発する
という点で、
社会という「メカニズム」に対する非難が
込められているということは、
一つの解釈として、
指摘することができるかもしれません。