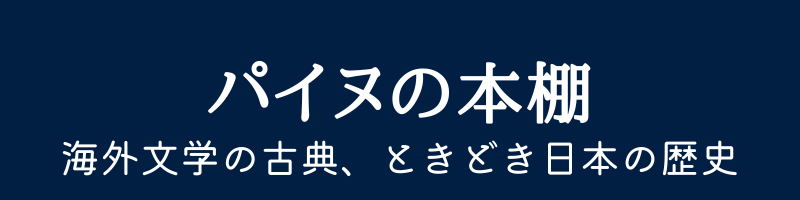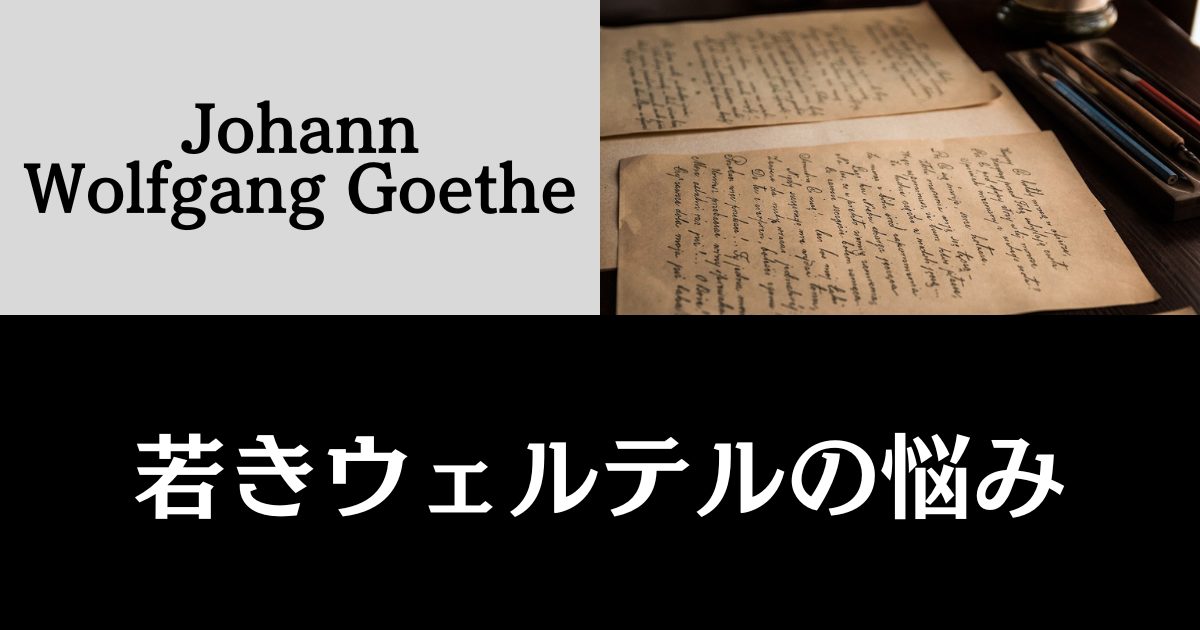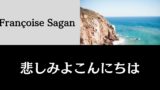TITLE : The Sorrows of Young Werther
AUTHOR : Johann Wolfgang Goethe
YEAR : 1774
GENRE : Bildungsroman, Youth
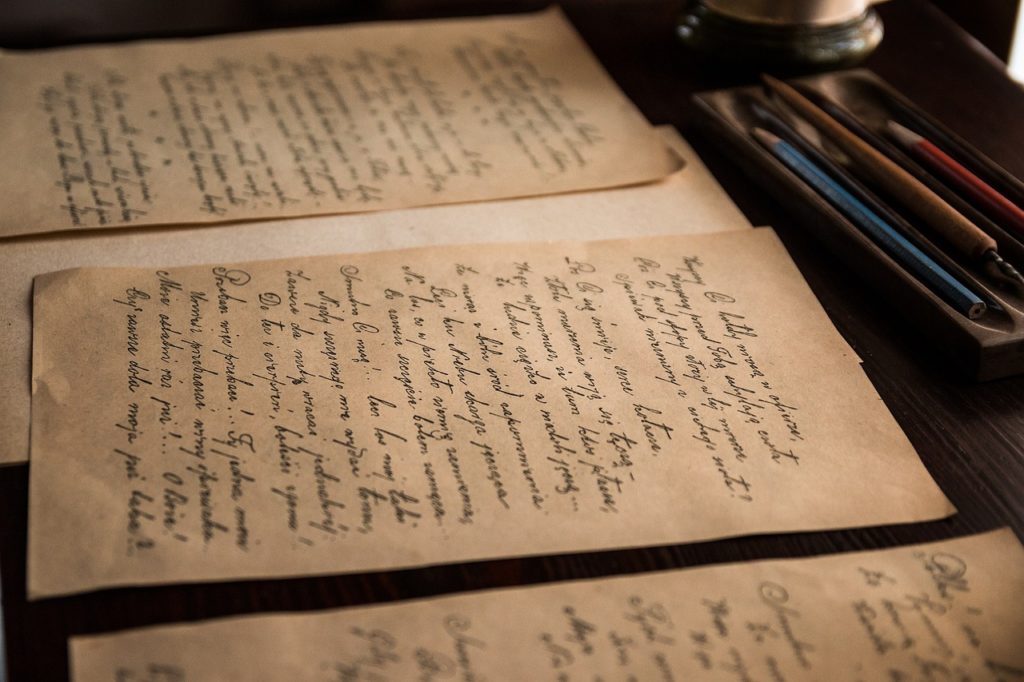
ぼくら教養ある人間は―実は教養によってそこなわれた人間なんだ。
P135(『若きウェルテルの悩み』ゲーテ著、高橋義孝訳、新潮社、1951年)
テーマ:自意識の副作用
【作品を読み解く3つのポイント】
1、嵐と衝動
2、書簡体の効果
3、失恋・失業・失望
【1】嵐と衝動
後年ゲーテは、「『ウェルテル』は、厭世という病的状態から生れたものであり、あの時代の病的風潮であったセンティメンタリズムを文学的に記録した小説である」と言っている。
P233(『若きウェルテルの悩み』ゲーテ著、高橋義孝訳、新潮社、1951年)
Sturm und Drang
(シュトゥルム・ウント・ドラング)
言葉としては、
Storm and Stress「嵐と衝動/圧力」
を意味しているとのことです。
その発端は、18世紀後半のドイツの文壇に
あるといいます。
啓蒙主義(個人+知識+理性)が形骸化し、
社会が、合理主義に走ることへの反発から、
主観に基づく自由な感情表現を重視する
文芸運動が活気を見せました。
この運動は、のちのロマン主義
(恋愛、幻想、民俗といった題材を好む)の
さきがけとなったといわれています。
ゲーテの出世作でもある
この『若きウェルテルの悩み』は、
そのような「嵐と衝動」の旗振り役として
当時の読者に大きな衝撃を与えました。
あなたって方は、どうしてまあこんなにはげしく、一度手をつけたことならなんにでも、どうしてこう情熱的にしつっこくなさるのでしょうね。
P179(『若きウェルテルの悩み』ゲーテ著、高橋義孝訳、新潮社、1951年)
本作において、この「嵐と衝動」の思想を
もっともよく体現していたのは、
深刻な悩みを抱え込んだ青年こと、
主人公ウェルテルでした。
親友に宛てた手紙のなかでも、
彼自身が、生来感情の起伏の激しい人間
であることを認めていますが、
のちに遭遇することになる2つの不運が、
そのようなウェルテルの気性を
さらに激化させることになります。
熱血漢とはまさしく、
ウェルテルのような人間を指すのでしょう。
出版から約250年後の現代を生きている
私パイヌの、一読者の感想としては、
ウェルテルの情緒不安定ぶりに
正直あきれてしまう気持ちもあるのですが、
社会を取り巻く思想の転換という観点から
この物語の効果を観察してみると、
ウェルテルにみられる気性の激しさには、
個人の意思(自由意志)を主張する
強固な姿勢を見て取ることができます。
【2】書簡体の効果
もしかすると、ウェルテルにみられる
やたらと極端に走る傾向には、
彼の性質ということ以外にも、
この「小説の形式」というものが
強く影響しているのかもしれません。
本作では、書簡体という形式を採用して
物語が進められていきます。
書簡体とは、手紙のやりとりを通して、
物語を断片的に展開していく手法のことを
いいます。
書簡体がもたらす効果としては、
一つには、手紙の書き手と、その読者の
心理的な距離感が縮まるということが
挙げられるでしょう。
要するに、ほかの叙述形式にくらべて
感情移入の度合いが増すのです。
ぼくはいろいろなことに堪えなければならん。ああ、ぼく以前でも人間はこんなに哀れなものだったんだろうか。
P153(『若きウェルテルの悩み』ゲーテ著、高橋義孝訳、新潮社、1951年)
こういう内包的(閉鎖的)な性質を持った
小説の形式に、
ウェルテルのような情熱的な主人公が
加わると、どうなるのかといいますと、
キャラクターの一挙一動が、
好感であれ、反感であれ、
読者に対して、扇情的な印象を
植えつけることになるのです。
そこへ、さらなる拍車をかけるのが、
本作のメインイベントでもある
ロッテとの悲恋の物語です。
激しい気質を持った男の、激しい片思いが、
彼自身の筆による手紙(書簡)を通して
伝えられることで、
読者は、かなりの至近距離から、
彼のほとばしるような激情を
目の当たりにすることになります。
この小説はまるで、
自分の気持ちを代弁してくれているような
気がする。
「ウェルテル効果」と呼ばれる
心理現象がありますが、
このような心理的な「同化」の誘発を
疑似体験できるという観点からしても、
本作は、非常に興味深い作品だと
いえるでしょう。
【3】失恋・失業・失望
「凡庸ならぬ人間」であるウェルテルには、
多くの人にとって、容易には理解しがたい
心理や行動がいくつも見受けられます。
しかし、その一方で、
彼が抱えていた悩みというのは、
時代の風潮や土地の習慣といった
それぞれの条件にかかわらず、
これまでにも、多くの若者を苦しめてきた
「よくある悩み」でもあったのです。
かなわぬ恋。
人間関係のストレス。
将来に対する不安。
ウェルテルを見舞った悲劇というのは、
一見すると、文学作品ならではの
特殊なケースのようでいて、
実のところ、程度の差はあれど、
人間誰しもが経験することになる
普遍的な苦悩のテーマを扱っている
ともいえます。
ぼくにはだんだん確かになってくる。確かに日増しに確かになってくる、人間の存在なんて何でもないんだ、まったく何でもないんだ。
P143(『若きウェルテルの悩み』ゲーテ著、高橋義孝訳、新潮社、1951年)
物語の冒頭、親友に宛てた手紙のなかで、
ウェルテルはすでに
傷心状態にあったことが暗示されています。
彼が故郷を離れた理由にも、
心機一転の目的があったようなのです。
このウェルテルの悩みの発端には、
「レオノーレの妹」なる人物が
深く関係しているらしいのですが、
その件については、多くを語っていません。
ウェルテルと「レオノーレの妹」の間に、
いったいなにがあったのでしょうか。
真相は定かではありませんが、
今回の不幸な出来事よりも以前に、
ウェルテルが追い詰められていた可能性は
高いといえるでしょう。
「刹那主義」というものは、
いつの時代もそうなのかもしれませんが、
多くの若者の心を惹きつけるようです。
過去でも未来でもなく、「今」を生きる。
しかしそこに、なにかしらの
倦怠感のようなものを
感じているのだとしたら、
その人は相変わらず、過去に引きずられ、
未来を憂いているのかもしれません。