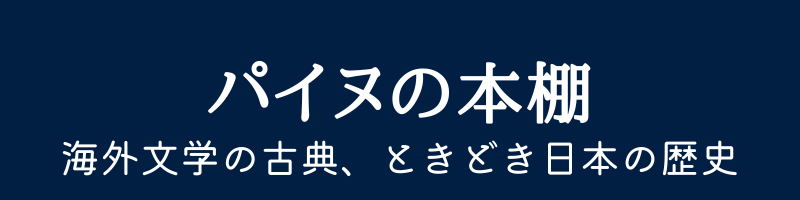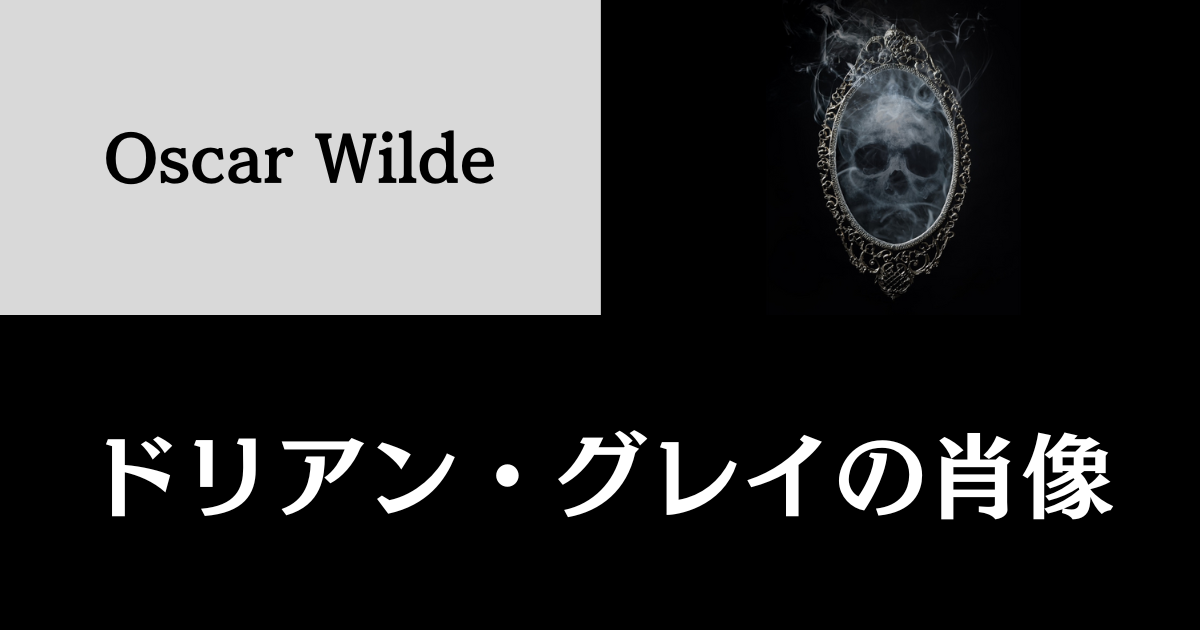TITLE : The Picture of Dorian Gray
AUTHOR : Oscar Wilde
YEAR : 1891
GENRE : Gothic Romance, Psychodrama

我々は不意に、自分がもはや演者ではないことに気づく。観客になっているのだ。あるいはむしろその両方といった方がいいかもしれない。我々は自分自身を見て、その見世物のすばらしさにただ魅了される。
P198(『ドリアン・グレイの肖像』オスカー・ワイルド著、仁木めぐみ訳、光文社、2006年)
テーマ:自意識の功罪
【作品を読み解く3つのポイント】
1、見る者と見られる者
2、ファウスト伝説
3、自意識の功罪
【1】見る者と見られる者
「彼はナルキッソスだよ。」
友人の画家バジルから、秘蔵の宝でもある
「ドリアン・グレイの肖像」を見せられた
ヘンリー卿は、
絵に描かれている人物を評して、
このように述べる場面があります。
この「ナルキッソス」という言葉が、
心理学の用語でもある
「ナルシシズム」の語源となったことは、
ご存じの方も多いことでしょう。
ちなみに、「ナルシシズム」には、
「自己愛」とか「自己陶酔」といった意味が
あるのですが、
これは、ギリシア神話に登場する
ナルキッソスという美少年が
水面に映し出された自分自身の顔に
一目惚れして、
恋に焦がれるあまり、寝食も忘れたため、
徐々に衰弱して死んでしまったという話に
由来しているとのことです。
こういうことを考えるのは悲しいが、才能が美より長生きするのは間違いない。(中略)熾烈な生存競争の中で、我々は何か長持ちするものを持ちたがる。そのためにくだらない事実の寄せ集めを詰め込む。愚かにもそれで、自分の場所を守れるんじゃないかと考えてね。
P31(『ドリアン・グレイの肖像』オスカー・ワイルド著、仁木めぐみ訳、光文社、2006年)
貧困層のための慈善事業にも携わる
心優しい青年であったドリアン・グレイに
「ナルシシズム」を目覚めさせたのは、
画家バジルが、心血を注いで描き上げた
美の傑作ともいうべき肖像画と、
ヘンリー卿が、音楽の甘い調べのような声で
とくとくと語る、美の教訓から芽生えた
強烈な「自意識」でした。
ここで興味深いのは、
画家バジルとヘンリー卿が指摘するまでは、
ドリアン・グレイは自身の美貌について
ほとんど無頓着であったということです。
「自分はこんなに美しいのだという思いが、
まるで啓示のように彼を襲った。
こんな気持ちは初めてだった。」
と心境を述べているように、
ドリアン・グレイは、
自分の肖像画と対面することで
はじめてその美貌を目の当たりにし、
同時に、ヘンリー卿によって植え付けられた
「美と若さのはかなさ」を悲観して、
恐怖におののくようになるのです。
美が彼を破滅させたのだ。あの祈りで手に入れた美と若さが。この二つがなかったら、彼の人生は汚れることはなかったのかもしれない。彼の美しさは仮面にしか過ぎず、若さは偽物でしかなかった。
P412(『ドリアン・グレイの肖像』オスカー・ワイルド著、仁木めぐみ訳、光文社、2006年)
このようなドリアン・グレイの変貌は
「見る者」と「見られる者」の
立場の逆転を暗示しているとも
考えられます。
以前には、その美貌を
「見られる=観察される」側であった
ドリアン・グレイですが、
2人の年上の男たちから、
美に対する意識を授けられたことで、
彼の立場は、自身の姿を
「見る=観察する」側へと移行します。
「見られる者」であったときには、
意識することがなかった事柄が
「見る者」となった瞬間に、
強烈に意識せざるを得なくなったのです。
こうして、ドリアン・グレイの身に起った
「意識の変革」は、
皮肉にも、純真な青年に
堕落と破滅をもたらすこととなります。
【2】ファウスト伝説
自分の魂と引き換えに、
あらゆる願望をかなえてもらう。
このようなモチーフは、
古今東西の文学のなかでも
頻繁に取り上げられていて、
もっとも有名な例としては、
ゲーテの『ファウスト』が挙げられます。
ちなみに、その主人公である
「ファウスト博士」にはモデルがいて、
15~16世紀のドイツに実在した
錬金術師であるとされています。
魔術によって召喚した悪魔と取引をして、
魂と肉体を差し出す代わりに
自分の望みをかなえてもらう契約を
交わしたとされるファウストですが、
彼の伝説が、ドリアン・グレイの悲劇にも
大きく影響しているということは
注目に値するといえるでしょう。
反対だったらいいのに!いつまでも若さを失わないのが僕のほうで、この絵が老いていけばいいのに!そうできるなら、そのためなら、僕は何だって差し出すよ。そうさ、この世の何だって差し出す!魂だって差し出すよ!
P56-57(『ドリアン・グレイの肖像』オスカー・ワイルド著、仁木めぐみ訳、光文社、2006年)
【1】のところで指摘した内容と
照らし合わせてみると、
ドリアン・グレイが
「ファウスト」であるならば、
画家バジルから贈られた肖像画と、
ヘンリー卿による美の洗脳が、
ファウストと取引をした
「悪魔」の役目を担っていると
指摘することができそうです。
もう少し踏み込んだ話をすると、
ゲーテの『ファウスト』と、
本作『ドリアン・グレイの肖像』では、
「魂(精神)と肉体の分裂」というのが
重要なテーマとなっていて、
「肉体の(即物的な)欲求」を
重視するあまり、
「魂の(精神的な)欲求」を
軽視した主人公が、
周囲の人々を不幸に陥れ、
しまいには己の破滅を招く様というのが
描かれているのです。
【3】自意識の功罪
人は自分を知り、自らを育てるために生きている。自分の本質を完全に理解する、そのために我々はここにいるのだ。最近では人々は自分をおそれている。あらゆる義務の中でもっとも大切な義務を忘れている。自分自身に負っている義務だ。
P41-42(『ドリアン・グレイの肖像』オスカー・ワイルド著、仁木めぐみ訳、光文社、2006年)
「いつまでも若さを失わないのが
僕のほうで、
この絵が老いていけばいいのに!」
ドリアン・グレイの切実な願望は
摩訶不思議な力によって
自然とかなえられていきます。
その間に、「美と若さのはかなさ」を教えた
ヘンリー卿の存在感は増大していき、
ドリアン・グレイは彼の価値観を
そっくり模倣するようになります。
ドリアン・グレイが身に着けた「教養」は
すべてヘンリー卿の受け売りであって、
さらには、そこから「堕落」という嗜好を
受け継ぐことになります。
このようにして、
「プリンス・チャーミング」から
「プリンス・パラドックス」へと
変貌を遂げたドリアン・グレイでしたが、
彼が、美しくあり続ければあり続けるほど、
また、賢くなればなるほど、
彼の「魂」からは純真さが失われ、
文字通り、身も心も、
「悪」の色へと染まっていったのでした。
美しくなればなるほど、醜くなるとは、
皮肉としか言いようがありませんが、
これもまた一つの、
逆説なのかもしれません。