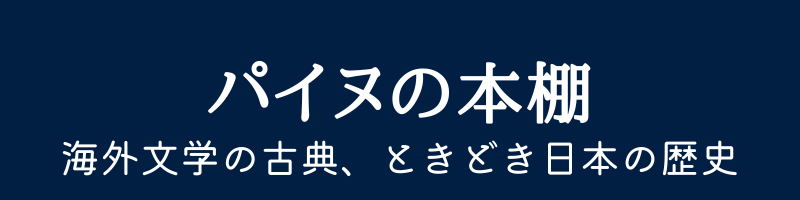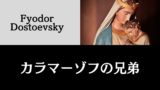TITLE : Terre des Hommes
AUTHOR : Antoine de Saint-Exupéry
YEAR : 1939
GENRE : Memoir

あれほど多くの星の中で、早朝の食事のこの香り高いひと碗を、ぼくらのために用意してくれる星は、ただ一つこの地球しか存在しないのだった。
P32(『人間の土地』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著、堀口大学訳、新潮社、1955年)
テーマ:孤高と孤独
【作品を読み解く3つのポイント】
1、マッチョな気質
2、天使の視点
3、大地のとらわれ
【1】マッチョな気質
「ぼくら人間について、大地が、
万巻の書より多くを教える。
理由は、大地が人間に抵抗するがためだ。」
本作『人間の土地』の冒頭に記された
この力強い格言は、
作者サン=テグジュペリ自身が、
郵便飛行士としての経験から獲得した
人類の宿命というものに対する一つの答えを
提示しているのかもしれません。
サン=テグジュペリの代表作はなにか?
と聞かれれば、やはり、
子どもから大人まで多くのファンを持つ
『星の王子様』(1943) を挙げる人が
ほとんどだと思います。
しかし、その一方で、
「サン=テグジュペリらしさ」なるものを
追求するとなると、
寓話として描かれた『星の王子様』よりも、
リアリズムと詩の融合という
特徴的な表現方法によって編み出された、
デビュー作『南方郵便機』や、
『夜間飛行』といった作品に尋ねるのが
的確であるといえるでしょう。
とりわけ、本作『人間の土地』で記された
郵便飛行士としての実体験や、
彼自身の思想からは、
等身大に近いサン=テグジュペリ像を
とらえることができそうです。
彼の職務の範囲内で、彼は多少とも人類の運命に責任があった。(中略)人間であるということは、とりもなおさず責任をもつことだ。
P63(『人間の土地』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著、堀口大学訳、新潮社、1955年)
サン=テグジュペリには、どことなく
ハードボイルドなところがあると
個人的には感じています。
ちなみに、私パイヌがこれまでに読んだ
サン=テグジュペリ作品というのは、
先ほど言及した4つの作品になるのですが、
これら4つの作品には、
登場する主要人物がほとんど男性である、
という特徴があります。
しかも、『星の王子様』を除く
ほかの3つの作品には、
物語のテーマとして、
郵便飛行士たちの命がけの任務や、
僚友(=戦友)の絆、といったものを
扱っているという共通点があります。
このように見ていくと、
サン=テグジュペリの作風には、
ヘミングウェイのそれにも似た、
いわゆる「男だけの世界」から生み出された
マッチョな気質を見て取ることが
できるのです。
ところがぼくは、ジーッという音を聞きつける、ぼくのランプに蜉蝣(かげろう)が突き当ったのだ。なぜというわけもなしに、この蜉蝣がぼくの心臓をつねる。
P115(『人間の土地』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著、堀口大学訳、新潮社、1955年)
このようなサン=テグジュペリの気質は
はたして、彼の幼少期を中心に
培われたものだったのか?
それとも、郵便飛行士という職業を通じて
形成されたものだったのか?
ということについては、
どうにも判断しかねるのですが、
少なくとも、郵便飛行士たちの負う任務が、
彼らに冷徹な姿勢を要求していたことは、
容易に想像することができます。
『夜間飛行』でも描かれたように、
航空会社が、所属する飛行士たちに
厳格な服務規程の徹底を命令するのは、
ちょっとした気のゆるみが、
任務の遂行を滞らせる恐れがあるからで、
最悪の場合には、機体や荷物だけでなく、
人命を失うという危険があるからです。
このような過酷な環境と厳格な習慣が、
飛行士でもあり、かつ作家でもあった
サン=テグジュペリの精神に、
飛翔することへのロマンと、
命の危機をはらんだ大自然のリアルを
刻み込んだのでしょう。
【2】天使の視点
新潮文庫版の巻末には、
文庫本の表紙のデザインを作成した
ジブリの宮崎駿による解説が
収録されています。
「充満する危険の中で、
張りつめ覚醒した彼等の見た世界は
どんな眺めだったのだろう。」
「空のいけにえ」と題された文章のなかで
宮崎駿は、このように述べています。
『人間の土地』に収録されている
8つのエピソードのなかでも、
とりわけ前半の4つにおいては、
サン=テグジュペリの
俗世間に対する冷笑的な態度が
際立っている印象を受けるのですが、
彼のそのような態度には、郵便飛行士たちの
覚めた(冷めた)視点というものが
強く影響しているのかもしれません。
はたしてぼくらは、人間そのものを批判するにあたっても、宇宙的な尺度をもって、科学者が拡大鏡をとおして見るように、機上の窓ごしに、見るように変(な)ってきた。はたしてぼくらは、いまにして人間の歴史を読みなおしているわけだ。
P74(『人間の土地』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著、堀口大学訳、新潮社、1955年)
「きみは人世の大問題などに
関心をもとうとはしない、
きみは人間としての煩悩を忘れるだけにさえ、
大難儀をしてきたのだ。」
地上の世界で、来る日も来る日も
些末な事務仕事に没頭する人々に対して、
サン=テグジュペリが向ける視線には
冷ややかなものがあります。
郵便飛行の運営と、その航路の開拓には、
「人類の進歩」に大きく貢献するという
誰に目にも明らかな、輝かしい英雄的な
偉業のイメージがあることは確かです。
とはいえ、そのような偉業の達成には、
名もなき人々の「影の努力」というものが
必要不可欠であったことは
言うまでもありません。
満天の星空、はてしない砂漠、
雪に閉ざされた山岳、ジオラマの大地。
地上のさまざまなものをとらえる
郵便飛行士の目であっても、
やはり、地上の多くの人々と同じように、
縁の下にあるものまで見通すことは
そう簡単には行かないようです。
【3】大地のとらわれ
普通、人は見ずにいる、人間を井戸につなぐ縄、臍の緒のように、人間を大地の腹につなぐその縄を。井戸から一歩遠ざかったら、人間は死んでしまう。
P212-213(『人間の土地』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著、堀口大学訳、新潮社、1955年)
では、サン=テグジュペリという人間は、
周囲の人々を虫けらのように軽蔑しながら、
自分を「神」のごとく錯覚するほどの
とんでもない傲慢の持ち主だった
のでしょうか?
いや、もちろんそんなことはないと
思います。
サン=テグジュペリが
冷ややかに見つめるのは、
「外」を知ろうとしない人々の怠慢です。
サン=テグジュペリの文明批判には
明らかに、共産主義や全体主義に対する
抵抗の意志が反映されていて、
その身近な例えとして、
自然界から隔絶された人工の蟻塚を
存在する唯一の世界であるかのごとく
盲信している人々に対する
怒りと失望があるのです。
「ぼくらは、食糧さえあれば満足する
家畜ではない」
勇猛果敢な飛行士サン=テグジュペリの
燃え盛る魂のメッセージが、
地下に潜り込んだ働き蟻たちの
耳元へ届くのは、
はたしていつになるのでしょうか。