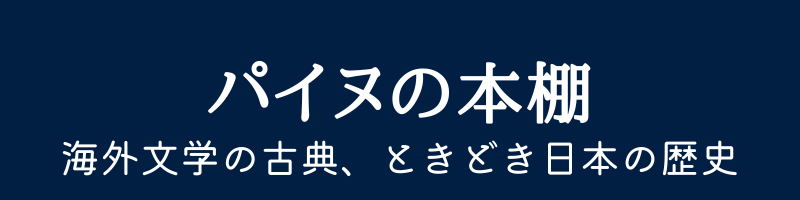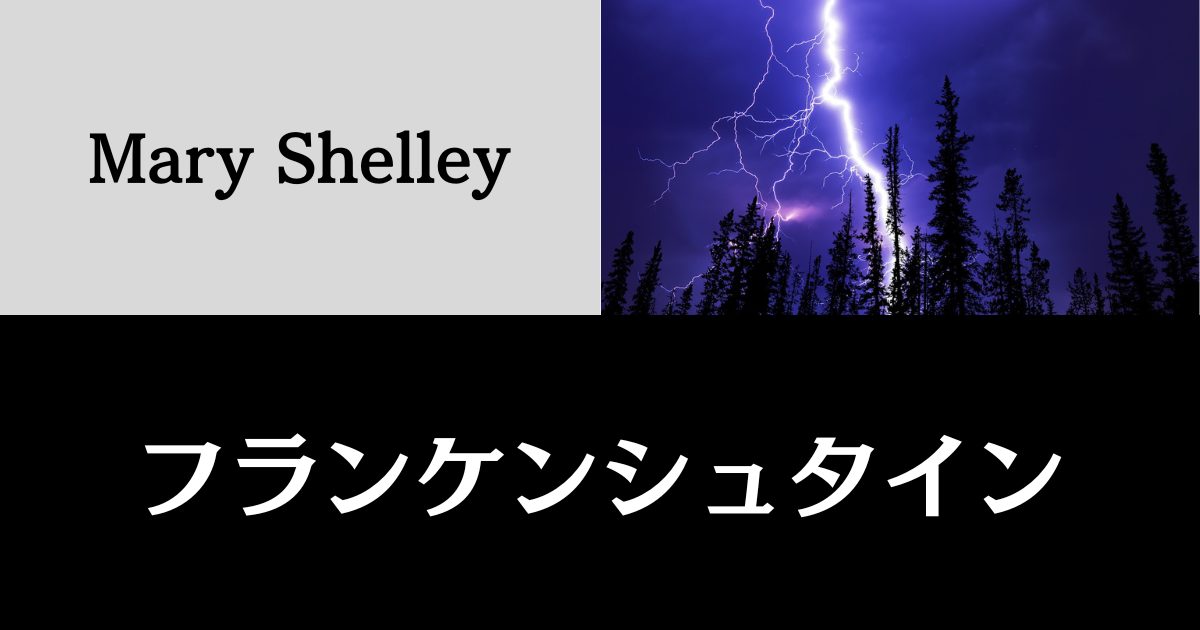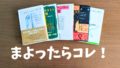TITLE : Frankenstein: or The Modern Prometheus
AUTHOR : Mary Shelley
YEAR : 1818
GENRE : Science Fiction, Gothic Romance

わたしの説教はともかく、せめてわたしの実例を見て学んでください。知識を得るのがいかに危険なことか、生まれた町こそ全世界だと信じこんでいる男のほうが、おのれの本性が許す以上のものになろうと憧れる男よりどんなに幸せかということをね。
P69(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
テーマ:知の苦しみ
【作品を読み解く4つのポイント】
1、ダーウィンとガルヴァーニ電流
2、母の不在
3、錬金術と科学
4、怪物から見た世界
【1】ダーウィンとガルヴァーニ電流
作者メアリー・シェリーは
本作の「まえがき」のなかで、
夫パーシ・シェリーとバイロン卿の間で
交わされた会話から
インスピレーションを受けて、
狂気の科学者「フランケンシュタイン」の
イメージを思いつくに至ったと
語っています。
そのとき、彼らは
「生命原理の本質」という問題について
意見を交わし合っていたそうなのですが、
この会話のなかで、
「ダーウィンの実験」と
「ガルヴァーニ電流の効果」が
引き合いに出されたといいます。
ちなみに、ここでいう「ダーウィン」とは、
『種の起源』(1859)の著者である
チャールズ・ダーウィンのことではなく、
チャールズ・ダーウィンの祖父にあたる
エラズマス・ダーウィンを指します。
エラズマスも、チャールズも、ともに
「進化(evolution)」という観点から
生物の成り立ちを分析しているのですが、
同じ「進化」でも、
双方の見解は異なっていたそうで、
エラズマスが「進化」という言葉に
「社会的な進歩・向上」の
意味を込めたのに対して、
チャールズは、あくまでも
「環境に適応するため」の変化の結果として
「進化」という言葉を用いた
とのことです。
おそらく屍をよみがえらせることはできるだろう。ガルバーニ電流がその証拠を示している。たぶん生物の構成部分を組みたて繋ぎあわせて、生命の熱を吹きこむこともできるのではないだろうか。
P10(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
それからもう一つ、
ガルヴァーニ電流についてですが、
文庫本の巻末の解説によると、
死んだカエルの足に電気を流すと
筋肉がぴくぴくと痙攣すること、
さらには、2つの異なる金属をあてると、
電気を流していないのに、
筋肉がぴくぴくと痙攣することから、
ガルヴァーニは、
「動物の中に内在する動物電気なるものが
回路を作ったのであろうと考えた。」
といいます。
しかし、のちにヴォルタの研究によって、
「電流は二種類の金属の接触によって
起こる」
ということが発見され、
ガルヴァーニの「動物電気」なるものは
存在しないことが証明されました。
進化論は神の否定につながり、そこから人間による生命創造の可能性も、当然、生まれてくるであろう。進化のプロセスがわかれば、人は神にかわりうるのではないだろうか。
P301(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
森羅万象は、唯一絶対の「神」によって
創造されたものであるとする
聖書由来の「創造論」に対して、
生物は、それぞれの環境に対応しながら
自分自身を変化させてきたと考える
ダーウィンの「進化論」は、
個体の意思に基づいた=神の意思に反した
そのような創造の可能性を示唆した
という意味において、
おもにキリスト教的な思想に対する
「冒瀆」であると考えることも
できるでしょう。
さらには、文庫本の巻末の解説のなかで、
解説者・新藤愛子が、
「現代のプロメテウスにとっての電気は、
神話時代のプロメテウスの火に相当する」
と指摘しているように、
ガルヴァーニの実験がもたらした
「電気」のインパクトというのもまた、
新たなテクノロジーを手に入れた人類に
「神の意思に背く行為」をそそのかす
「禁断の知恵」となったと
いえるのかもしれません。
【2】母の不在
さて、ここで一つ、
「フランケンシュタインの悲劇」にまつわる
メインストーリーから少し離れて、
この物語に登場する「女性の存在」に
焦点を当ててみたいと思います。
フランケンシュタインとその怪物が
直接的あるいは間接的に
関わることになる女性たちには、
ある特徴が見受けられます。
それは、彼女たちが人生の早い段階で
「母親を失っている」ということです。
本作には主要人物として、
カロリーヌ、エリザベス、ジュスティーヌ、
アガサ、サフィー、という
5人の女性が登場しますが、
それぞれが話に登場した時点ですでに、
彼女たちは自分の母親と
死別しているのです。
「母の喪失」ということに関して言えば、
母カロリーヌを失った
フランケンシュタインとその弟たちや、
アガサの兄フェリックスについても
同じ立場に変わりないのですが、
家庭における「役割」を考えたとき、
登場人物の男性と女性とでは
立場がまったく異なってくることが
わかります。
女性たちには、
「娘」「妹」「妻」といった立場に加えて、
「母」として家庭を切り盛りする役割が
与えられていて、
母亡き後にあっては、
その「代理」として振舞うことが
求められているのです。
いっそあなたと一緒に死ねたらいい。こんな悲しい世界に、わたし生きてはいけないわ
P118(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
それからもう一つ、
「母の不在」というテーマに関連して
指摘しておきたいのが、
フランケンシュタインと怪物の
「いびつな親子関係」についてです。
文庫本の巻末の解説にもあるとおり、
フランケンシュタインと怪物の間には、
「親子の関係」または「それ以上の愛憎」が
見受けられます。
しかし、ここのところで
強調しておかなければならないのが、
この2人の親子関係には
「母の存在」が欠けているということです。
本来人間は、親との離別があったとしても、
自分という存在をこの世に生み出した
父と母を持っている生き物ですが、
フランケンシュタインの怪物には
「母」なるものが存在しません。
それもそのはずで、その生みの親である
フランケンシュタインは、
「母」の存在をまったく無視したまま
(あるいは「女」の力を借りることなく)
自らの手で(「男」一人の力によって)
「子」を誕生させたため、
彼らの親子関係には
端から「母(女)」が存在しないのです。
自分のために女を創造してもらいたい。ともに暮らして、生きるのに必要な心の共感を交わせる相手を創ってほしい。
P190(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
娘の誕生後、ほどなくしてこの世を去った
メアリー・シェリーの母親は、
『女性の権利の擁護』という著書を
発表していることからもわかるように、
「フェミニストの先駆者」でもありました。
本作に登場する女性たちが
早くから自分の親元を離れるという
境遇にあったのは、
彼女たちが
「親の支配」から離れている人間として
特徴づけられているからなのかも
しれません。
このような女性たちの描き方には、
亡き母の意思を受け継いだ
娘のメアリーの理想が投影されていると
考えることもできるでしょう。
廣野由美子著
『批評理論入門:『フランケンシュタイン』
解剖講義』
ジョン・サザーランド著
『ジェイン・エアは幸せになれるか?』
といった有名な批評本のなかでも、
本作に関する「フェミニズム批評」が
取り上げられているのですが、
このようなフェミニズム的な視点は、
メインストーリーの裏側に潜む
忘れられた「女」と「母」の面影を
浮かび上がらせるとともに、
作者メアリー・シェリーの
フェミニズムの思想を際立たせます。
【3】錬金術と科学
子どもの頃から探求心旺盛で、
「自然の隠れた法則」を解き明かすことに
情熱を注いできたフランケンシュタイン。
そんな彼の人生を大きく変えることとなった
最初の出来事として、
「錬金術」との出会いがありました。
旅行先の宿屋で、何気なく手に取った
コルネリウス・アグリッパの本に
フランケンシュタイン少年は
強い衝撃を受けます。
アグリッパの著作を
「時間の無駄、駄作」といって嘲笑する
父の言葉になかば逆らうようにして、
少年は錬金術の世界へ
のめり込んでいきます。
「究極の原因」を見極めることよりも、
「分析し、解剖し、命名する」ことに
終始する近代の科学に対して
不満と退屈を感じていた彼でしたが、
大学へ進学してからは、
今や「論破された体系」となった
錬金術を捨てて、
より現実的(論理的)な化学の道を
志すようになります。
とはいえ、子どもの頃からの夢であった
「創造のもっとも深い神秘を
世界に解き明かしてみせる」ことを
すっかりあきらめてしまったわけでなく、
近代の科学(化学)にも、
そのような偉業を達成する可能性が
十分残されていることを知ると、
フランケンシュタインの情熱は
再び燃え上がるのでした。
天才の仕事というものは、どんなに方向を誤ろうと、窮極においてはまず間違いなく人類のたしかな利益に転ずるものでね。
P64(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
錬金術の本来の目的は、
不老不死の霊薬と
賢者の石(卑金属を貴金属に変える触媒)を
発明することだったと言われています。
古代ギリシアや、古代エジプトにまで
時代をさかのぼることができるほどに
古い歴史を持つ錬金術ですが、
Wikipediaの説明によると、
錬金術の研究対象は、金属に限らず、
「人間の肉体や魂」にも
範囲が及んだことが記されています。
ちなみに、古今東西において、
人類が求めてやまない「不老不死」ですが、
もしそれを現実に手に入れることとなれば、
人類に究極的な破滅をもたらす
「死」を克服することになります。
聖書のなかでは、
人類の祖にあたるアダムとイヴが
神によって禁じられていた
「知恵の樹の実(=善悪の知識)」を
食べてしまった(手に入れた)ことで、
神の怒りを買い、
楽園を追放された経緯が語られています。
「知恵の樹の実」には、
不老不死を奪い去る効果があったため、
この出来事をきっかけに、人類は、
「いずれ必ず死ぬ」という運命を
背負うことになったというわけです。
アダムとイヴを楽園から追放した
神の側からすれば、
自らの過ちによって失った不老不死を
人類がもう一度取り戻そうとするのは、
神に対するさらなる「反抗」を意味します。
新しい種はわたしを創り主、みなもとと讃え、あまたのすぐれた幸せ者たちがこのわたしから生を受ける。わたしが彼らから受けるべき感謝は、世の父親が子に要求しうるよりもさらに完璧なものなのだ。
P70(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
「自分は何か大偉業をなす運命にあると
信じていた」
探検家ウォルトンに対して、
このように語った
フランケンシュタインでしたが、
そのような彼の野心には、
「神への反逆」をも辞さない
強固な意志のようなものがうかがえます。
「迷信やお化け、暗闇といったものに
おびえた記憶がない」
とまで言い切る彼にとっては、
「タブーを破る」ことに対する抵抗感など
単なる些事にすぎないものだったのかも
しれません。
このようなフランケンシュタインの
「合理主義」的な性格には、
錬金術や科学の性質が
そっくりそのまま反映されているような
印象を受けます。
いかなる犠牲を払ったとしても、
自身の目的(理想)は
必ず達成されなければならない。
そのような姿勢というのは、一見すると、
「栄光と名誉」という輝かしい実績を
約束してくれるようにも思われますが、
フランケンシュタインを見舞った悲劇にも
如実に表れているように、
多くの場合、それが
取り返しのつかない大惨事の
引き金となることは
周知の事実でもあります。
【4】怪物から見た世界
だが、わが創り主よ、おまえが被造物のおれを憎み、はねつけるのか。どちらかが滅びぬかぎり切っても切れない縁で結ばれているわれわれなのに。それを殺そうというのだな。どうしてそんなふうに命をもてあそぶことができるのだ?
P133(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
文庫本の巻末の解説によると、
フランケンシュタインと怪物の関係性を
「ドッペルゲンガー」として解釈する
見方もあるといいます。
そのなかで解説者も指摘しているとおり、
この2人の関係性には、
ポーの『ウィリアム・ウィルソン』を
彷彿させるものがあります。
ここで興味深いのは、
『ウィリアム・ウィルソン』と同様に、
片方が「悪」の側面を
もう片方が「善」の側面を
それぞれ体現していることです。
『フランケンシュタイン』の場合、
フランケンシュタインと怪物のうち、
どちらが「善」で、
どちらが「悪」に相当するかは、
それぞれの視点によって変化しています。
つまり、フランケンシュタインの視点は、
自身の立場を「善」として、
彼とその周囲の人間に対して
極悪非道を働く怪物を
「悪」とみなしているのに対して、
怪物の視点は、それとは正反対に、
「創り主」の身勝手や無責任を挙げて、
彼の「悪」をとがめているのです。
世にある無数の人間のなかに、おれを哀れみ、助ける者はひとりもいない。敵に対して優しい心を持てというのか?否。その瞬間から、おれは永遠の戦いを宣言したのだ。人類に、そしてとりわけ、自分を創り、このしのびがたい苦悩のなかへ送りだしたその男に。
P179(『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著、森下弓子訳、東京創元社、1984年)
「創造主と被造物」という
2人の関係に照らし合わせれば、
フランケンシュタインへの復讐に燃える
怪物の行動は「神に対する冒瀆」に値する
といえるでしょう。
その一方で、フランケンシュタインは、
「生物の創造」という神のみが成し得る業を
手に入れることによって、
神の尊厳を冒しました。
そのような意味においては、
フランケンシュタインも怪物も同様に
神に対する「反逆者」なのです。
「知識がふえればふえるほど、
自分がいかにみじめなけものかが、
いよいよはっきりするだけだった。」
己の正体を、実態よりも高く評価した
フランケンシュタインは、
自身を「神」とみなし、
己の正体を、実態よりも低く評価した
怪物は、
自身を「サタン」とみなしました。
「自分とはいったい何者なのか?」
それを知った2人の男は、道こそ違えども、
ともに「神の意思」から逸れることを
選択したのでした。