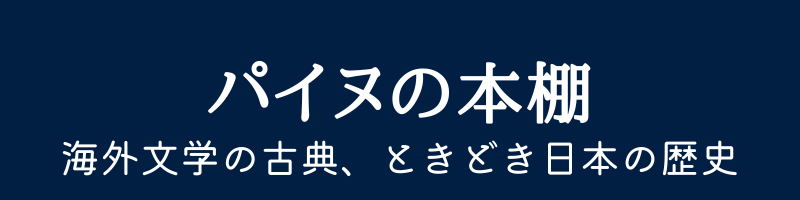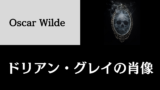TITLE : Death in Venice
AUTHOR : Thomas Mann
YEAR : 1912
GENRE : Aestheticism

芸術家というものの本質と特徴との謎を解けるものがいるだろうか。芸術家の実体をなす、規律と放逸が深く本能的に融合している状態を誰が理解するだろうか。
P86(『ベニスに死す』トーマス・マン著、圓子修平訳、集英社、2011年)
テーマ:肉体の解放
【作品を読み解く4つのポイント】
1、母の面影
2、奇妙な男たち
3、美少年の魔性
4、死の予感
【1】母の面影
相反する2つの性質。
『トニオ・クレーガー』でも描かれた
この板挟みと葛藤のテーマは、
トーマス・マンという作家の「深淵」を
形成していたといえるかもしれません。
とりわけ興味深いのは、
このようなアンビバレンスが
その両親の家系に起因して、
主人公の性格に表れているという点です。
本作の主人公アシェンバハもまた、
トニオ・クレーガーと同様に、
ドイツ人の堅気な父親と、
異国(ボヘミアとイタリア)出身の
芸術家肌の母親のもとに生を受けます。
性急な、官能的な血は一世代前に、つまりボヘミアのある楽長の娘である詩人の母によって、この一族にもたらされた。詩人の外貌に外国人ふうの特徴があるのは、この母のせいである。
P17(『ベニスに死す』トーマス・マン著、圓子修平訳、集英社、2011年)
貴族の身分を賜るという栄誉により、
名実ともにドイツの国民的作家となった
アシェンバハですが、
そんな彼の作家生活を支えていたのは、
父親の家系から脈々と受け継がれた
規律と勤勉の性質でした。
その一方、ミステリアスで情熱的な
母親の気質はというと、
現在のアシェンバハからは
すっかり消え失せてしまったようです。
そのような状況のもとへ、
降って湧いたのが「遁走の衝動」でした。
ヴェニスを訪れるまでの経緯には、
彼の身に起きた性質の逆転現象を
見て取ることができます。
「遁走の衝動」をきっかけに、
アシェンバハの無意識のなかで、
「父なるもの」から「母なるもの」への
移行が開始されるのです。
それは同時に、威厳と名声の作家、
「フォン・アシェンバハ」のなかに、
母の面影がよみがえった瞬間でも
ありました。
【2】奇妙な男たち
このようなアシェンバハの心境の変化は、
彼が遭遇した「奇妙な男たち」によって
徐々に具体化されていきます。
ここでいう「奇妙な男たち」とは、
物語のなかで実際に登場した、
旅人のような風貌の赤毛の男と、
若造りをした商店員の男を指します。
まず、物語の冒頭で、
散歩帰りのアシェンバハが、
斎場の入口に立っているのを目撃したのが
赤毛の男です。
その男の、異国風の外観に触発されて、
アシェンバハはイタリア行きを決心します。
そして、ヴェニスへ向かう船で
乗り合わせたのが、
もう一方の、若造りをした商店員の男です。
無理な若造りをして、年甲斐もなく
若い同僚と羽目を外すこの男に対して、
アシェンバハは強い不快感を覚えます。
孤独はまた倒錯したもの、不均衡なもの、愚かしく許すべからざるものをも産み出す。
P45(『ベニスに死す』トーマス・マン著、圓子修平訳、集英社、2011年)
良くも悪くも、強烈な印象を残した
この男たちとの出会いは、
彼がヴェニスに到着したあとになって、
もう一度「再現」されることになります。
おそらく同じ人物と思われる赤毛の男が、
彼の滞在先のホテルにやってくる
大道芸人の座長として再登場しています。
他方、若造りをした老人はというと、
理容室で美顔術を施された
アシェンバハ本人の容姿を借りて
再現されています。
ここで注目したいのが、
彼らの最初の遭遇と、
その次の再会との間に見られる
シチュエーションの違いです。
ヴェニスに到着する前と後では、
アシェンバハ自身の言動もずいぶんと
様変わりしていることがわかります。
最初に遭遇した際には、
それぞれの男たちとの出会いが、
アシェンバハにとって異国への誘いを
意味しました。
ところが、その次に出会ったときには、
状況そのものが一変しています。
美少年の虜と化したアシェンバハと、
コレラに侵されたヴェニスの町にとって、
この男たちの出現(再現)は
「死」を意味していたのです。
【3】美少年の魔性
精神の遁走先ヴェニスで、
アシェンバハは「タジオ」と呼ばれる少年と
出会います。
この少年は家族とともに
ポーランドから保養に来ていて、
彼と同じホテルに滞在している
観光客のなかの一人でした。
ギリシア彫刻のような「完璧な美しさ」に
驚嘆と恍惚感を覚えたアシェンバハは、
直接的な接触はあえて避けつつも、
少年の姿を執拗に追い求めるように
なります。
そして、この美少年の発見が、
威厳と名声の作家アシェンバハの心理に
劇的な変化をもたらすことになるのです。
たしかにわれわれはたとえわれわれの流儀で英雄であり、紀律正しい戦士であるとしても、女性なのだ。なぜなら情熱はわれわれを高めてくれるものだから。そしてわれわれの憧れはかならず恋なのだから。―これがわれわれの快楽であり、恥辱なのだ。
P130-131(『ベニスに死す』トーマス・マン著、圓子修平訳、集英社、2011年)
物語が終盤に差しかかる頃には、
アシェンバハの、少年に対する執着心も
異様さを帯びてくるようになります。
P120-123で展開される悪夢の場面には、
彼の心理にうごめく倒錯と恐怖の拮抗が、
狂気の沙汰として描かれています。
非常に興味深いことに、アシェンバハが
就寝中に見たというこの悪夢は、
ギリシア神話に登場する、
葡萄酒と酩酊の神ディオニュソスの
狂信的な信者が行っていたとされる秘儀を
連想させます。
フリードリヒ大王の英雄的生涯を歌い上げた
国民的人気作家が、
異教の神を祭り上げる儀式に陶酔する。
美少年が醸し出す耽美の誘惑は、
彼の克己心をいともたやすく打ち砕き、
その深奥に抑圧された情欲の炎を
瞬く間に煽り立てたのでした。
【4】死の予感
アシェンバハは、コレラの蔓延の事実を
知っていたにもかかわらず、
美少年に対する愛惜の気持ちから
最後まで出国を躊躇していました。
最終的に、それが彼の命取りとなったことは
言うまでもありません。
しかし、俯瞰してこの物語を眺めてみると、
実のところ、ヴェニスを訪れる以前から
すでに、彼に死の兆候が表れていたことが
わかります。
先ほど言及した「奇妙な男たち」の登場は、
そのもっとも顕著な兆しといえるでしょう。
物語の冒頭で、赤毛の男と出会う場面では、
「墓碑」「墓地」「斎場」といった
「死」を連想させるモチーフが頻出します。
一方で、若造りをした老人に対する
アシェンバハの反応には、
「老い」というものへの嫌悪と抵抗が
露骨な形で表されているのです。
ヴェネツィアのゴンドラに乗り込むとき、かすかな戦慄、内心の不安と当惑を感じないひとがいるだろうか。(中略)独特な黒色の、この世にあるもののなかでは棺だけがそれに似ているこの異様な乗物、(中略)いや、それ以上に死そのものを、棺台と陰惨な埋葬と、最後の、無言の野辺送りとを想い起させる。
P38(『ベニスに死す』トーマス・マン著、圓子修平訳、集英社、2011年)
アシェンバハ自身は、はたして
その身に忍び寄る命の限界を
察知していたのでしょうか。
美少年に対して見せた、あの異様な執着心は
「生」の願望の現れだったのでしょうか。
真相は定かではありませんが、
象徴的な意味における「死」のイメージが、
ヴェニスという異国の土地に
彼を引き寄せたことは間違いなさそうです。
人生の終わりが近づくにつれて、
威厳と名声の作家アシェンバハは、
「形式」という呪縛から解放され、
「放埓」の境地へと導かれていきます。
そこで、彼が目の当たりにしたのは、
美しいものの限界と、
その向こう側に広がる
計り知れない暗黒の世界でした。